 その2へ
その2へ
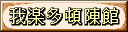
 webmaster@snap-tck.com
Copyleft (C) 2000 SNAP(Sugimoto Norio Art Production)
webmaster@snap-tck.com
Copyleft (C) 2000 SNAP(Sugimoto Norio Art Production)
時は第1次世界大戦の真っ最中、イギリスはウェールズ地方の小さな村に、地図作りのために政府から派遣された測量技師がやってきます。 その村には村人達が昔から誇りにしている小さな山があったのですが、その技師が測量したところ、イギリス政府の規定による「山」の最低高度1000フィート(305m)に20フィート(約6m)ほど足らず、「山」ではなく「丘」と判定されてしまいます。 それを聞いた村人達は、村の名誉と誇りを守るためドン・キホーテ的行動に出ることにしたのですが……という実話に基づいた、イギリス映画らしいユーモア溢れる傑作です。
実話に基づいているとは言うものの、馬鹿馬鹿しいことを真面目くさってやってしまう、奇妙なユーモア精神の持ち主であるイギリス人のこと、どこまでが実話でどこからがホラ話なのか区別がつきがたく、練達の手に成る上質な大人のメルヘンといった作品になっています。 この映画を見ると、何となく、真面目くさった顔で冗談を言い、落ち着き払って悪ふざけをする、端倪すべからざる英国紳士を連想してしまいます。
もし僕が映画を撮るとしたら、こんな感じの作品を撮りたいですねぇ。
恥ずかしながらこの映画のことはほとんど知らなかったのですが、僕の好きなモーガン・フリーマン(「ドライビング・ミス・デイジー」や「セブン」に出演した渋い黒人俳優)が出ていましたので、何気なく観たところ、思いのほかしみじみとしたいい映画でした。
無実の罪で投獄された元銀行副頭取の主人公(ティム・ロビンス)が、長い年月をかけて執念で脱走するというメインストーリーに、老服役囚(モーガン・フリーマン)との奇妙な友情や、刑務所長の汚職などといった話をからめた渋い刑務所物で、意外なことに原作はあのスティーブン・キングでした。 キングは「キャリー」や「シャイニング」などのモダンホラー作家として有名ですが、この作品や「スタンド・バイ・ミー」のようなドキュメンタリータッチの地味な秀作も書いているのです。
また刑務所物と言えば「大いなる幻影」、「大脱走」、「パピヨン」、「蜘蛛女のキス」などといった作品を思い出しますが、どちらかと言えば、派手なハリウッド物よりもヨーロッパ映画のような淡々とした映画が好みの僕としては、この作品は「蜘蛛女のキス」と共にお気に入りの刑務所物になりそうです。(^^)v
井伏鱒二の原作を今村昌平監督が映画化したもので、原爆後遺症をテーマにした重厚な作品です。 白黒の映像が淡々とした調子と時代背景にうまくマッチして、不思議にリアルな印象を残します。
今村昌平監督と言えば「神々の深き欲望」、「復習するは我にあり」、「楢山節考」などの作品に代表されるように、人間のドロドロとしたエゴや欲望をリアルに描くことを得意としています。 しかしこの作品は原作の淡々とした作風を意識してか、ところどころにシニカルな笑いを交えながら、かなり抑えた調子で描いています。 このシニカルな喜劇タッチは今村作品の特徴のひとつであり、「幕末太陽伝」で有名な師・川島雄三監督から受け継いだものでしょう。
今村昌平監督好みの渋い演技派俳優が揃っている中で、僕の好きな”芸達者な近所のおばさん”山田昌がなかなかいい味を出しています。
アメリカの、とある砂漠地帯の寂れたガソリンスタンド兼モーテル「バグダッド・カフェ」に、ある日、大きな旅行かばんを抱えた太ったドイツ人女性ジャスミンがフラリとやってきます。 何やら謎めいたところのある彼女の出現にカフェの人達と常連客は……といったことから始まる、ほのぼのと心温まるこの奇妙な物語は、一言で言えば大人向けのメリーポピンズといったところでしょうか。
美人でもなく可愛くもなく、その上、ふくよかすぎる中年太りという、およそヒロインらしからぬキャラクターでありながら、物語が進むにつれて妙に可憐で魅力的に見えてくる主演の怪女優マリアンネ・ゼーゲブレヒトと、哀愁漂う主題歌「コーリング・ユー」が実にいい味を出しています。
メルヘンと呼ぶにはあまりに奇をてらった演出の多い奇抜な作品ですが、こういった一風変わった大人のメルヘンが僕は大好きです。(^^)v
まるで江戸川乱歩の怪奇小説か、梅図かずおの怪奇マンガを連想させる題名ですが (^^;)、アルゼンチンの作家マヌエル・プイグの異色小説をブラジルのバベンコ監督が映画化した異色の刑務所物です。 ファシズムが支配する南米の刑務所を舞台に、現実主義者の政治犯(ラウル・ジュリア)と、かつて観た映画の世界にひたるホモセクシュアルの男(ウィリアム・ハート)とが、奇妙な友情を芽生えさせていく様子を、現実と空想とを交錯させながら描いていて、幻想的でペシミスティックな情感が漂う中に、不思議な救いを感じさせるラストが胸を打ちます。
「アダムス・ファミリー」の家長役でお馴染みのラウル・ジュリアが、現実主義者の政治犯役を硬派な演技で演じているのも見ものですが、「愛は静けさの中に」の先生役や「ドクター」の医者役など、クールで誠実な二枚目役が売りのウィリアム・ハートが、現実逃避型のホモセクシュアル役を熱演しているのは一見の価値があります。
ピュリッツァー賞作家ウィリアム・スタイロンの小説を映画化したもので、アウシュビッツのユダヤ人強制収容所から生還した女性ソフィーの波乱に満ちた哀しい物語です。 何しろ原作が長く複雑なもんですから、エピソードをやや詰め込み過ぎの感もありますが、テーマを正面きって声高に叫ぶかわりに、戦争の傷跡を背負って生きるひとりの女性の生きざまを、静かにそして哀しく描いていて深い感動を残します。
作品の急所急所に出てくる、やむにやまれぬ”ソフィーの選択”は、そうすることによってしか激動の時代を生きのびることができなかった無力な女性の哀しい生涯を象徴していて印象的です。
ソフィーを演じたメリル・ストリープはこの作品でアカデミー主演女優賞を受賞しましたから、ご存知の方も多いでしょう。 彼女の繊細で哀しげな美しさは、まさに適役のような気がします。
10年に1本しか映画を撮らない寡作監督ヴィクトル・エリセの長編第1作で、現実と幻想が交錯する叙情的かつ神秘的な作品です。 エリセ監督の映像センスの鋭さが光る映像詩的な画面構成と、少女アナを演じるアナ・トレントのあどけない可愛らしさが特に印象に残ります。
この映画だけでなく、「禁じられた遊び」、「鉄道員」、「自転車泥棒」、「汚れなき悪戯」等々、ヨーロッパ系の映画の子役は実にあどけなくて可愛らしいキャラクターが多く、しかも伝統的に子役の使い方が巧みな気がします。 それに対して、「ペーパームーン」、「レオン」、「ホームアローン」、「タクシードライバー(この映画のジョディ・フォスターを子役と呼ぶのは少々無理か!?(^^;))」等に代表されるように、アメリカ映画の子役がどちらかと言えばこまっしゃくれていたり、大人びていたりするのはお国柄の違いでしょうか。
もちろんヨーロッパ系の中にも「地下鉄のザジ」のような作品がありますし、アメリカにも「キッド(チャプリンは元々イギリス人ですが)」や「チャンプ」のような作品がありますから、単に僕の観た映画が偏っていただけかもしれませんが…。(^^ゞ
それにしても、まるで成人映画を思わせる「ミツバチのささやき」という邦題は、何とかならんもんでしょうかねぇ。(^^;)
1966年、水爆を塔載したアメリカ空軍のB52戦略爆撃機がスペインのパロマレス沖に墜落します。 アメリカ空軍の発表によれば水爆は無事に引き上げられたということですが、その詳しい経緯は全く発表されず、本当に水爆が無事に引き上げられたかどうかは、当のアメリカ国内においてさえ強い疑惑が持たれました。 この墜落事件は当時のヨーロッパを震撼させ、世界中で話題になりましたのでご存知の方もあると思います。 この事件に触発されて、「その男ゾルバ」で有名なギリシャの巨匠、マイケル・カコヤニス監督が製作・脚本・監督をした作品がこの「魚が出てきた日」です。
墜落事件に触発されたと言っても、水爆の恐ろしさを声高に叫ぶわけでも、大国の傲慢さに正面切って抗議を唱えるわけでもなく、表面上は近未来を舞台としたスラップスティック風SFに仕立て上げておきながら、凡百の反戦論など吹っ飛ばしてしまうほどの強いインパクトを感じさせるところが、巨匠カコヤニス監督の非凡なところです。
とにかくユーモアありドタバタありでゲラゲラ笑わされたあげく、最後のシーンで背筋をゾォ〜ッとさせられます。 このラストシーンは、「猿の惑星」の印象的なラストシーンと並んでSF映画名ラストシーンの双璧だと思います。
そう言えばこの作品が公開されたのと同時期(1968年)に、SF映画の2大名作である「2001年宇宙の旅」と「猿の惑星」も公開されています。 当時高校生だった僕はこれら3作品から強烈なインパクトを受け、大いに影響されまくりました。
進行性筋萎縮症という難病にかかり、数々の奇行、奇癖、酒席での破天荒なエピソードを残して44才で夭逝した鬼才、川島雄三監督の代表作で、古典落語の「居残り佐平次」、「芝浜」、「品川心中」などを下敷きにして、軽佻浮薄な中にも独特のシニカルな視点を持った喜劇映画の傑作です。
原作の落語と違って主役の佐平次は労咳(肺結核)持ちという設定になっていますが、これは主役のフランキー堺のアイデアで、自身も難病持ちの川島監督に気に入られて採用されたそうです。 またラストシーンで、川島監督は台本(脚本・今村昌平)を無視して、佐平次をスタジオの中から外へ、さらに撮影所の外まで飛び出させようというアイデアを出したそうです。 このアイデアはさすがにスタッフに止められて、結局は台本通りになりましたが、この映画を撮り終わった後、彼は日活を止めてフリーになっていますので、そんな彼の気持ちが反映されたアイデアだったのかもしれません。
川島監督はこの作品や「貸間あり」などの喜劇ばかりでなく、「雁の寺」や「青べか物語」などの文芸物にも取り組んで格調の高い作品を残し、愛弟子の今村昌平をはじめ、後輩の監督達に大きな影響を与えています。
ラジウムの発見者として有名な女性科学者マリー・キュリーの伝記映画で、彼女の娘であるイーヴ・キュリーが書いた優れた伝記「キュリー夫人伝」を下敷きにしています。 科学者の伝記物ですが、科学的な業績よりもピエール・キュリーとマリー・キュリーの夫婦愛と人間性を主軸にしていて、しみじみと心温まる作品となっています。
マリー役のグリア・ガースンは、その知的で端正な美貌から”クール・ビューティ”と呼ばれていましたが、この作品ではその個性がうまく生かされていてなかなかの適役です。 また、後に「禁断の惑星」でエキセントリックなマッドサイエンティストを演じることになるウォルター・ピジョンが、純真素朴な科学者ピエールを好演しています。 このキャラクターは、「レナードの朝」でロビン・ウィリアムズが好演したセイヤー博士と並んで、僕のお気に入りの科学者キャラクターです。(^^)v
それにしても第2次世界大戦まっただ中の1943年に、大戦の主要国であったアメリカで、夫婦愛とヒューマニズムをテーマにした、このような映画が作られていたという事実には少なからず驚かされます。 その頃の日本映画といったら、戦意高揚のために作られた、軍部からのお仕着せ軍国主義映画一色でした。(~_~)