
 その6へ
その6へ
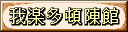
 webmaster@snap-tck.com
Copyleft (C) 2000 SNAP(Sugimoto Norio Art Production)
webmaster@snap-tck.com
Copyleft (C) 2000 SNAP(Sugimoto Norio Art Production)
30年前、毎朝のラジオ体操を拒否したために大手電機会社を解雇され、それ以来、抗議のために会社の前で毎朝プロテストソングを歌い続けている田中さん。 その田中さんと彼の支持者達の姿を通して見えてくる現代日本の姿を、オーストラリアの女性監督マリー・デロフスキーがユーモアたっぷりに映しだす傑作ドキュメンタリー映画です。
期待以上の内容に感動し、上映後に田中さん本人のトークと歌を聞き、サインをもらいながら色々と話をさせてもらい、田中さんのエネルギーを少しおすそ分けしてもらって、僕も久々に反戦フォークを歌い、昔のように学生運動をしたくなりました! p(^o^)
すでに絶滅してしまったと思っていた反権力主義、反体制主義、反金儲け主義、反経済優先主義、反ビジネス中心主義、反マスコミ主義の人達が、実はまだしぶとく生き残っていて、相変わらず(本人にすれば)素直で、かつ(他人から見れば)へそ曲がりな生き方を貫いていることに大いに共感し、大きな勇気をもらいました。 僕も、これからも人の言うことには耳を貸さず、いやだと思ったことは断固として拒否し、我儘で唯我独尊の生き方を貫き通そうと、あらためて思いました。 v(^o^)
上映後に田中さんが歌った「人らしく生きよう」という歌の中の、印象的な歌詞を書いておきます。 著作権侵害になるかもしれませんが、田中さんのCDを購入したことに免じて許してもらいましょう。 (^^;)
「平成ジレンマ」で一部のコアな映画ファンに強烈な印象を与えた、阿武野勝彦監督の最新ドキュメンタリー映画です。 戸塚ヨットスクールの現在を圧倒的な迫力で描いた「平成ジレンマ」と違い、四日市喘息という公害の歴史を淡々と描写することによって、観客に深くて重い思考を促す作品になっています。
この作品は福島の原発事故の前に完成していましたが、期せずして、福島の原発事故について深く考えさせられる内容になっています。 これは、責任の所在を曖昧にするために「公害」という言葉を作り出した経済最優先の社会構造が、昔も今も全く変わっていないからであり、大都市の経済的繁栄が、その周辺の町の住民の犠牲の上にアグラをかいたものであることを再認識させられます。
この作品の主人公の一人である澤井余志郎氏は、四日市喘息の患者達を支援する活動を40年にわたって無償で続けてきた人であり、「何よりも事実は強い」という信念に基づいて、事実を記録してそれを人に伝えるという活動を現在も継続している”公害記録人”です。 この人の信念と活動内容、そしてその成果を見ていると、ジャーナリズムとマス・メディアあるいはマスコミは全く別物だということがよくわかります。
またもう一人の主人公である野田之一氏は公害裁判の原告の一人であり、38年前、公害裁判で勝訴した時に、支援者に対して「まだ、ありがとうとは言えない。この町に本当の青空が戻った時、お礼を言います」という強烈なメッセージを残した、元漁師の喘息患者です。 この人は公害裁判を企業対患者、権力対個人というステレオタイプな対立構図に落とし込まず、次のようにもっと大きなものとして捉えています。
「日本が敗戦の混乱から高度経済成長に向けて突っ走り、強引に近道をしようとしたために無理が生じた。
その無理が産み出したものが公害なのだ。
コンビナートで働く人達も、みんな日本のために良かれと思って必死に働いてきたのだから、コンビナートやそこで働く人達を憎いと思ったことはない。
ただ無理が何をもたらすかを知ってもらい、一度立ち止まって、それについてみんなで考えてもらうために我々は公害裁判を起こした。
コンビナートで働く人達が悪玉で、我々患者が善玉というわけでは決してないのだ」
「エコロジー」や「ボランティア」という外来語よりも、「もったいない」や「お互い様」という日本語の方がしっくりくるのと同様に、「デモクラシー」や「市民活動」という外国の概念よりも、このように「お互い様」という考えに基づいた懐の広い活動こそが日本の市民活動のあるべき姿だと思います。
この野太くておおらかなヒューマニズムに対して、企業の経営者や行政は、
「コンビナートを止めると日本経済が大打撃を受け、日本が潰れてしまう。 日本の繁栄のためには多少の犠牲はやむを得ない」
第二次世界大戦前、政府と軍部は「満州は日本の生命線であり、これを手に入れないと日本が潰れてしまう」と主張して中国に侵略しました。 そしてその結果、日本は戦争に敗れましたが、政府と軍部が主張したように日本が潰れることはなく、むしろ第二次世界大戦前よりも繁栄しています。 これは、独裁政治をやめて民衆の権利を認め、戦争を放棄して平和に暮らし、財閥による富の独占をやめて民衆に富を公平に分配すれば、国全体が繁栄するという見事な実例です。
公害についても、企業が公害対策に費用をかけたために企業が潰れ、日本が潰れるということはなく、環境が改善して労働条件も向上したため、長い目で見ればむしろ企業の業績は向上し、当時に比べて暮らしやすく豊かな社会になっています。 こういった歴史を振り返ると、企業の経営者や行政が「日本のため」と言いながら、その実、自分達の目先の利益しか考えておらず、いかに近視眼的かつ利己的かということがよくわかります。
誰もが原発問題について否応なく考えざるを得ない今、この映画を多くの人に観てもらいたいと思います。
東西ドイツ統一前後の東ドイツを舞台にした、味わい深い人間ドラマの秀作です。 完成度の高い脚本と全編にみなぎる静かな緊張感、そして国家保安省(シュタージ)のエリート捜査官を淡々と演じる主演のウルリッヒ・ミューエが実に巧く、ラストカットの彼の一言のセリフと表情には、思わず涙ぐんでしまうほど感動しました。
人は誰でも理想を抱くと思いますが、社会の激流に流されてその理想を忘れてしまいがちです。 何かおかしい、これは自分の理想とは違うと感じた時に、当面の利害や我が身の保身といったものに流されてその違和感を黙殺するか、それとも勇気を出して正しいと思う道を選ぶか、人は誰でも多かれ少なかれ人生の中でそういった岐路に立たされる時があると思います。
そういった時に社会の激流に流されず、良心に恥じない選択をするのは非常に難しいことです。 しかし良心に恥じない選択をした人は、たとえそのために大きな犠牲を払うことになったとしても、自分に対する誇りを失わず、胸を張って人生を生きられるはずです。 ラストカットのウルリッヒ・ミューエの一言のセリフと表情は、そのことを見事に表現しています。
この作品といい、ヴォルフガング・ベッカー監督の秀作「グッバイ、レーニン!」といい、激動の歴史を経験した国からはやはり味わい深い傑作が生まれるようです。
それから思いがけずこの作品に、「マーサの幸せレシピ」で生真面目な女性シェフを好演していたマルティナ・ゲデックが出ていました。 この作品では大人の魅力溢れる妖艶な女優を演じていて、最初は彼女とわからないくらいイメージが違うのでビックリしてしまいました。 生真面目な彼女も妖艶な彼女も、どちらもまるで地のように見せてしまう彼女の演技力に脱帽です。m(..)m
久しぶりに大いに楽しませてもらった、日本の傑作コメディ映画です。(^o^)/
「12人の怒れる男」を意識したと思われる、舞台劇のような完成度の高いワン・シチュエーションドラマであると同時に、愛すべきアイドルオタク達の生態を暖かい眼差しで描いたアイドルオタク映画としても出色のできです。 とにかく脚本がよく練られていて、ワン・シチュエーションドラマのツボをしっかりと押さえつつ、コメディベースにミステリー風味を加え、最後にホロリとさせるところなど実に巧いものです。
ただ、おそらくあまりに上手にまとめすぎることに監督自身または脚本家自身が照れたのだと思いますが、最後にハチャメチャを入れて照れをまぎらし——これは、観ている方も照れから救われる気分になるのでまだ許せます——、さらに余分な蛇足オチ——これは、この手のコメディの定番オチではありますが——まで入れてしまったのは少々残念です。
また5人の登場人物を演じる俳優達——小栗旬、ユースケ・サンタマリア、小出恵介、塚地武雅(ドランクドラゴン)、香川照之——は、香川照之以外は正直言って少々演技力不足ですし、あまりオタクっぽくありません。 しかし演技力不足を演出の良さでうまく補っていますし、オタクではない観客(特に女性!(^_-))にも受けるように、あえて「オタクらしくない美男子のオタク」を狙ったキャスティングなのでしょう。
香川照之が演じているキャラが立ちまくった役は、本来は竹中直人が適任でしょう。 でも他の4人が少し弱いため、彼が演じると場をさらってしまうので、竹中直人よりはアクが弱く、他の俳優の個性を殺さない香川照之にしたような気がします。
この作品は最初は舞台劇として上演され、それが映画化された後で、改めて舞台劇として再上演されたそうです。 これだけよく練られた完成度の高い脚本ですから、舞台劇として、演技力のある俳優によってきっちりと演じられるところを観たい気がします。
「痴呆老人の世界」や「安心して老いるために」などの作品で有名な記録映画作家、羽田澄子監督のドキュメンタリー映画の秀作です。
自身が満州からの引揚者である羽田監督は、筆舌に尽くしがたい苦労の末に日本に引き揚げてきた人達や、引き揚げ時の混乱で孤児になり、中国人に命を救われた残留孤児達を訪ね、日本の敗戦前後の逃避行の実態を淡々と、しかし執念と気迫を込めて浮かび上がらせていきます。
羽田監督のインタビューに答える人達は、彼女が醸し出す独特の雰囲気と優しさに包まれ、彼女を信頼し切った様子で淡々と本音を語っています。 その等身大の姿は、ドラマや演出過多のドキュメンタリーでは決して見られないものであり、僕の両親が折にふれて満州からの引き揚げの様子を語ってくれた姿とダブって見えて、とても人事とは思えませんでした。
エッセイコーナーに展示してある「行雲流水」を書くために資料を色々と調べたので、満州からの引揚者と残留孤児についてある程度のことは知っているつもりでした。 しかし恥ずかしながら、この作品の主要なテーマである「方正(ほうまさ)地区日本人公墓」のことは、この作品で初めて知りました。
詳しい説明は会議室の書き込みをご覧いただくとして、この公墓は、旧満州で悲惨な最期を遂げた満州開拓団の人達のために、中国政府が建立してくれたものです。 侵略された国が、侵略した人達の墓を建立して墓守を置き、ナショナリズムの激流に押し流されることなく、国際主義的な精神から長年の間維持管理してくれているのです。
戦争によって多くの日本人が犠牲になった場所は、中国だけでなく、朝鮮半島、シベリア、東南アジア等々、沢山あります。 しかし、侵略者である日本人のために公墓を建立してくれた国は、唯一、中国だけでしょう。
またそれらの場所では、日本人の犠牲になった現地の人達が、日本人の犠牲者以上に数多く存在します。 しかし日本政府は、それらの人達のために公墓を建立するようなことはしていませんし、ましてや自国に侵略した侵略者のために公墓を建立し、それを長年の間維持管理するなどということは決してしないでしょう。
これらのことを考えると、中国人の懐の深さにあらためて感動し、中国人の大人(たいじん)ぶりに比べれば、日本人はまだまだほんの子供にすぎないと、つくづく思い知らされます。 そしてそれと同時に、国と国がナショナリズムを高揚させて争うことが、どれほど馬鹿げたことであるかということを痛感させられます。
羽田監督は「この映画を作り終えて、大きな重い宿題をひとつ果たした気持ちだ」と述べています。 満州からの引揚者である彼女にとって、この作品は特別な思い入れのある作品なのでしょう。 そして引揚者の子供である僕にとっても、この作品は特別な思い入れのある作品になりました。
「スター・トレック」へのオマージュ全開のSFパロディで、「スター・トレック」とトレッキーに対する愛情、そしてSFに対する愛情に溢れた、文句のつけようがない傑作です!(^o^)/
シガーニー・ウィーバーとアラン・リックマン(イギリスのシェイクスピア俳優、「ハリー・ポッター」のスネイプ先生で有名)、そしてお気に入りのトニー・シャルーブ(知る人ぞ知る、「名探偵モンク」!(^_-))以外はあまり馴染みのある俳優が出演しておらず、いかにもB級映画っぽいチープな雰囲気をかもし出しています。 しかしB級映画っぽいチープな雰囲気を確信犯的に狙いつつ、その実、細部まで綿密に作り込まれた、笑いと涙と感動の堂々たる正統派コメディーです。
製作者とスタッフと出演者の熱気、そしてみんなが楽しんで映画を作っていることが作品のいたるところから感じられ、最後の感動的な大団円では、思わず拍手喝采して感涙にむせんでしまいました。 チャップリンの「街の灯」のラストを観て泣かない人、あるいはこの作品の大団円を見て拍手喝采しない人がいたとしたら、僕はその人とは友達になれそうもありません。(^^;)
不幸にして、この傑作をまだ観ていないトレッキーやSFファンがいたとしたら、すぐにDVDを借りてきて観賞することをお勧めします。
では最後に、お約束の、
「Never give up ! Never surrender ! p(^O^)」
東西冷戦時代からベルリンの壁の崩壊、東西ドイツの統一といった激動の時代の東ドイツを舞台に、時代の波に翻弄されながらも、健気に生きる庶民の姿をコミカルに、そしてほろ苦いペーソスと淡い郷愁を込めて描いた秀作です。 ベルリンの壁の崩壊から十数年経って、ようやくこのような映画ができた、というか、十数年経たなければこのような映画を作ることができなかったということからも、東西ドイツの統一が東ドイツの人達に与えた影響の大きさがわかります。
この作品を観ると、たとえイデオロギーや国家の形態が異なっていても、その中で健気に生きる庶民の心情は、どこでも変わらないものだということがわかります。
自国と他国を比較する時、ややもすると、他国についてはイデオロギーや国家の形態といった表層的なものだけを見て、その国の特徴と考え、自国についてはよく知っている身の回りの人間や生活環境を見て、自国の特徴と考えて比較してしまうことがあります。 例えば、自国の国家権力や政治家については批判的で、自国の長所は国民の勤勉さと真面目さだと考えている人が、他国については、国家権力や政治家だけを見てその国の特徴ととらえて批判する、といったことがあります。
これは別次元のものを比較しているのですから、公平な比較であるはずがありません。 この作品を観ると、庶民はどの国でも健気に生きていて、そういった庶民の姿を知らない限り、公平な比較はできないという、当たり前のことを再認識させられます。
これまでに観たドイツ映画の中では、ヴィム・ヴェンダース監督の作品と並んで、お気に入りの作品になりました。(^o^)v
中国の内モンゴル自治区にあるモンゴル高原を舞台にした、雄大な叙事詩のような作品です。 監督は、中国映画界で”おしどり夫婦”として有名なマイ・リースとサイ・フで、この2人はどちらも内モンゴルの出身です。 そして監督だけでなく、俳優も主要なスタッフも内モンゴル出身者ばかりのため、内モンゴルの人々の暮らしぶりや民族性が忠実に描写され、祖国と草原に対する愛情に溢れた感動的な作品になっています。
アジア映画にはまるで故郷に帰ったような懐かしさを感じる作品が多く、同じような民族性であることを強く実感させられます。 この作品はそういった懐かしさだけでなく、何か魂の故郷といった感じがして、自分でも不思議なほど深く感動し、作品を観ながら胸が震えるような思いが何度もしました。
ストーリーそのものはありがちで、例えば山田洋次監督の「幸せの黄色いハンカチ」や「遥かなる山の呼び声」などを連想させ、登場人物も高倉健や倍賞千恵子などを髣髴とさせます。 しかし雄大なモンゴルの草原を舞台にし、おおらかでたくましく、素朴で寛容な人間愛に溢れた遊牧民達の物語として描かれているため、まさにこの世ならぬ天上世界を舞台にした叙事詩を映画化したような感じを受けます。
この作品にこれほど感動した理由は、僕のDNAに組み込まれているであろう北方系モンゴロイド遺伝子のせいかもしれません。 僕のオヤジさんは遊牧民が好きで、満州で馬賊になるのが夢だったそうです。 ひょっとしたら僕にも、そういった遊牧民好きの血が流れているのかもしれません。
その血のせいか登場人物達に深く感情移入してしまい、映画が終わっても、まるで大河物語の最初の章が終わっただけであり、この後も彼等を主人公にした長い長い物語が続くような気がしました。 そしてモンゴル高原に行けば彼等に会うことができ、アイラグ(馬の乳から作った酒)の入った杯を傾けながらその後の物語を語ってくれそうな、そんな気がしてなりませんでした。
いやぁ、アジア映画は本当にいいですねぇ〜!p(^o^)
タイで大ヒットした話題作であり、タイの大学のマスコミ学部の卒業生6人による共同監督という珍しい作品です。 まるで30年前の日本映画を観るような、いやもっとはっきり言うと、子供時代に読んだ少年漫画を思い出させるような懐かしさに溢れた作品です。 幼馴染の女の子との淡い初恋、男同士の友情、ガキ大将の存在、隣町のグループとの対立等々、少年漫画の王道テーマが衒うことなく語られていて、懐かしさに胸がキュンキュンしまくります。
同じアジアのせいか、登場人物達のキャラクター設定と性格描写に違和感が全く無く、風俗もまるで古き良き時代の日本のようで違和感がほとんどありません。 その上、 土管が積まれた原っぱで子供達がゲームをしたり、みんなで駄菓子を買って、それ食べながら自転車でたむろしたりと、僕らの子供時代を髣髴とさせるようなシーンが次から次へと出てくるので、昔の日本の少年漫画を映画化した作品を観ているような錯覚にとらわれてしまいます。
これは、おそらく監督達の中に日本の漫画が好きな人がいて、その影響を受けているせいではないかと思います。 その証拠に、作品中にドラえもん、キャンディ・キャンディ、あさりちゃんといった日本の漫画作品が出てきて、子供達がそれに夢中になっている様子がそれとなく描かれています。 そして子供達のキャラクターも、ジャイアン、スネ夫、のび太、そしてしずかちゃんを連想させるような設定になっていて、顔を見ただけで役柄と性格がわかります。 またヒロインの少女が、美少女ではないものの、実に素朴で可憐で可愛らしく、すっかりファンになってしまいました。
いやぁ、アジア映画はやっぱりいいですねぇ〜!v(^o^)
17世紀のオランダの画家フェルメールの絵をモチーフにした作品で、イギリス在住のトレイシー・シュヴァリエの小説を映画化したものです。 フェルメールはオランダを代表する画家のひとりであり、この作品のモチーフになっている「真珠の耳飾りの少女(青いターバンの少女)」や、「牛乳を注ぐ女」などの作品が有名です。 しかし彼は生前はあまり評価されておらず、後世になって再評価されたせいか、彼の作品とされるものは世界中に40点足らずしか知られておらず、その生涯についても不明な部分が多いそうです。 このあたり、何となく浮世絵師の写楽を連想させますね。
この映画は小説の映画化というよりも、フェルメールの絵を動く映画にしたといっても良いほどに絵画的です。 とにかく緊張感のある見事な映像美と、それを引き立てる音楽の素晴らしさに圧倒されてしまい、最初から最後までため息の連続でした。 ヨーロッパ映画の映像センスと音楽センスの素晴らしさには、やはり伝統の力を感じます。
またヒロインの少女を演じているスカーレット・ヨハンソンは、決して僕好みではありませんが(^^;)、妖しく背徳的なエロスを濃密に漂わせていて実に魅力的です。 そしてそんな彼女の魅力を、フェティッシュで暗示的なカメラワークが余すところ無く描き切っていて絶妙です。 特に彼女が耳にピアスの穴を開け、真珠の耳飾をつけるシーンは、暗喩というよりも直喩といったほうが良いほど露骨にエロスを暗示していて、R指定になっていないのが不思議なほどです。 これで、もしスカーレット・ヨハンソンが僕好みだったら、僕的には間違いなくX指定ですね。v(^^;)