
 その5へ
その5へ
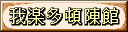
 webmaster@snap-tck.com
Copyleft (C) 2000 SNAP(Sugimoto Norio Art Production)
webmaster@snap-tck.com
Copyleft (C) 2000 SNAP(Sugimoto Norio Art Production)
「スウェーデンの子供映画」という理由だけで観た作品ですが、期待にたがわず実にいい映画でした。 最近1年間で観た映画やアニメの中では、「東京ゴッドファーザーズ」(今敏監督)と並んで抜群に良かったため、誰かに聞いてもらいたくて紹介することにしました。
スウェーデンの子供映画といえば、僕のお気に入りの「マイライフ・アズ・ア・ドッグ」と「やかまし村の子どもたち」(どちらもラッセ・ハルストレム監督)、そして「イノセント・ライフ」(アーケ・サングレン監督)と、珠玉の名作が揃っています。 これは、スウェーデンには優れた児童文学があることと無関係ではないでしょう。 例えば「やかまし村の子どもたち」の原作と脚本を書いているアストリッド・リンドグレーンは世界的に有名な児童文学者であり、この作品よりも「長くつ下のピッピ」や「ロッタちゃん」がよく知られていると思います。
スウェーデン以外にも、フィンランドには「ムーミン」で有名なトーベ・ヤンソンがいましすし、デンマークにはハンス・クリスチャン・アンデルセンがいます。 このように北欧の国々は伝統的に児童文学が盛んなため、子供映画にも優れた作品が目白押しです。 そしてヨーロッパ映画の伝統に従い、どの映画も子役の使い方が巧みで、演技が自然です。とにかく出てくる子供たちが、アメリカ映画のように変にこまっしゃくれていなくて、実に好感が持てます。 ハリウッド風ジェットコースター映画に食傷気味な人には、特にお勧めです。(^_-)
少し異常な世界を題材にして、その中からいかに普遍的なものを引き出すことができるかという挑戦を確信犯的に続ける、アルモドバル監督らしい話題作です。 「オール・アバウト・マイ・マザー」よりもさらにきわどいところを狙っているため、好き嫌いがよりはっきり分かれる作品でしょう。
しかしアルモドバル監督の映像センスと音楽センスはますます鋭くなっていて、際物から昇華した抽象美のようなものを感じます。 特に冒頭と最後のドイツの舞踏家ピナ・バウシュによる舞踏シーンと、中ほどのブラジルの歌手カエターノ・ヴェローゾが「ククルクク・パロマ」を歌うシーンは実に印象的で、これらのシーンだけでも十分に見ごたえがあります。
前作とこの作品で、アルモドバル監督はお気に入りの監督のひとりになりました。 この人の作家性と映像センス、そして音楽センスには非凡なものを感じます。(^^)v
少し異常な世界の人達の生活を、暖かい視線で描いた佳作です。 ラテン系、闘牛、情熱といったキーワードで語られることの多いスペインなのに、この映画や「ローサのぬくもり」のように、映画はなぜかこういったしっとりとした作品が多いように感じます。 スペイン民謡には不思議と哀愁漂う曲が多いのですが、それが何となく納得できるような気がします。 そしてスペインと同じようにラテン系のはずのアルゼンチン映画の救いようの無い暗さと、哲学的瞑想というイメージが強いインド映画の能天気な明るさには驚かされます。 こういったことを考えると、「ラテン系」や「インド的」というような単純なラベル化が、いかに表層的なものにすぎないかがわかるような気がします。
また「オープン・ユア・アイズ」で印象的な役をやったペネロペ・クルスが、またしても印象的な役をやっています。 この2作品を見ただけで、この女優が今や売れっ子になっている理由がわかる気がします。
いやぁ〜、いい映画でした! 久しぶりに、本当に久しぶりにアメリカ映画で泣かされました。 もともとこういった家族物には弱いところにもってきて、DVDレコーダーの録画機能チェックのために手当たり次第に録画した作品のひとつであり、ほとんど期待していなかったので、不意打ちにあったように感動してモロに泣かされてしまいました。(;_;)
地味ながらツボを押さえたキメの細かい演出、渋くて芸達者な俳優陣、味のあるカメラワーク、しっとりとした叙情的な音楽、そして何よりも作中人物に対する作り手の暖かく優しい眼差しが、ありがちなテーマにありがちなストーリー展開の物語を心に残る感動的な作品にしています。 今のアメリカ映画界にこんな渋くて味のある映画を作る人がいるとは……と、自分の無知を棚に上げてちょっと驚いています。(^^;)
ただ、ついでにつけたような散文的な邦題は少々いただけません。 原題は「Autumn Heart」とこの作品にふさわしくて詩的なのですから、もう少ししっとりとした詩的な邦題をつけて欲しかった気がします。 この作品と似たテーマを扱った萩尾望都の初期の短編漫画に、「秋の旅」という名作があります。 その題名をパクって、「秋の旅」とか「秋の帰郷」といった邦題の方がしっくりくると思います。
ニキータ・ミハルコフが監督、主演、脚本、製作の4役を兼ねた意欲作で、「シベリアの理髪師」と並ぶ傑作です。 スターリンの独裁時代をテーマにしているため、ややもすると暗く生真面目で重い作品になりがちなところを、美しい映像と美しい音楽に彩られたユーモアあふれるチェーホフ的な人間ドラマにしていて、しかも深い感銘と強いメッセージを感じさせるところがさすがにミハルコフです。
ミハルコフ監督がこの作品に力を入れていることは、4役を兼ねているだけでなく、「シベリアの理髪師」にも出演しているお気に入りの名優オレグ・メンシコフと、6歳になる彼の愛娘ナージャ・ミハルコフを出演させていることからもわかります。 ナージャ・ミハルコフの汚れない透き通った笑顔と、演技とは思えないほど自然で愛らしい仕草は、重いテーマと過酷な運命を暗示するこの作品の中で強く印象に残ります。
「シベリアの理髪師」はテーマが恋愛であり、ミハルコフ監督が肩の力を抜いて自身も楽しんでいるため、気楽に楽しめる涙と笑いの感動作になっているのに対して、この作品は重いテーマに真摯に取り組んでいるため、多少肩に力が入っている感じで気楽に楽しむというわけにはいきません。 しかしロリコン殺しの美少女ナージャ・ミハルコフの透き通った笑顔と愛らしさは、テーマの重さを補って余りあり、彼女見たさについつい何度も観てしまいました。(^^;)
ガロ系耽美派漫画家の花輪和一が、自身の刑務所体験を基にして描いた話題の獄中記マンガを崔洋一監督が映画化した作品です。
花輪和一のフィルターを通過したため、淡々とした中にもとぼけたユーモアとペーソスと妖しい凄みのあるものになっているユニークな刑務所生活の描写が、さらに崔洋一監督のフィルターを通すことによって凄みの代わりにほのぼのさが加わり、より一般人向けな作品になっています。 マンガファンの僕としてはやっぱり原作の方が好きですが、主演の山崎努の秀逸な独白的語りにだけは脱帽しました。
実はこの作品は監獄博物館のある網走で長期ロケをしていて、娘の大学の演劇部の学生がエキストラで出たり、娘がアルバイトをしているファミリーレストランにスタッフや俳優が食事に来たりしたということを娘から聞いていたので、製作中から特別な興味を持っていました。
そして刑務所に入る前の生活を描いた冒頭のシーンで、僕がひいきにしている網走の海産物土産屋の袋を山崎努が持っているのを見て、思わず嬉しくなってしまいました。 このシーンは原作でも映画でも網走という設定ではないですから、山崎努本人かスタッフの誰かがその海産物土産屋で買い物をし、たまたまその袋を映画の小道具として利用したんでしょうね。(^^;)
ん?「シベリアの理髪師」?「セビリアの理髪師」の間違いじゃないの……? と思って観てみたら、これがパロディと文芸物、爆笑と号泣、愛と感動のめったやたらと面白い大河巨編でした。(^O^)(ToT)(^^;)(;o;)
現代ソ連映画を代表する名監督ニキータ・ミハルコフの名前は聞いたことがあったものの、恥ずかしながら作品を観るのはこれが初めてでした。 しかしトルストイを思わせる雄大さ、チェーホフを思わせる深さはさすがはロシアという感じで、黒澤明やジョン・フォードなどの偉大な名監督と同じようなスケールの大きさと風格を感じさせるところがあります。
この作品を観て、ニキータ・ミハルコフはたちまち僕のお気に入りの監督の一人になりました。 映画を観て思いっきり笑い、思いっきり泣き、ジーンと感動したい人には是非お勧めしたい傑作です。
マジッド・マジディ監督の最新作で、「運動靴と赤い金魚」と並ぶ珠玉の作品です。 クスリと笑わせ、ホロリと泣かせ、しみじみと感動させる、実にいい映画です。 貧しくとも心豊かで思いやりと優しさにあふれていた古き良き時代の日本映画を思わせる、本当にいい映画です。
「運動靴と赤い金魚」とこの作品を観て、イランやアフガニスタンについて自分がいかに何も知らないか、いかに偏見の目で見ていたかがわかり、恥ずかしさを感じるとともに猛烈に反省させられました。 この作品を、イランやアフガニスタンを「悪の枢軸国」と決めつける独善的な権力者や、それに追従する欺瞞的な政治家達に見せてやりたい気がします。 しかしそういった人達には、この作品が描いている庶民の生活は、富も権力も無いものの、健気でつつましく心の豊かさと思いやりに満ちた心情は決して理解できないでしょう。
我々日本人は、欧米、特にアメリカのフィルターを通して知らされるニュースや映像を見ているうちに、知らず知らずのうちに世界を歪んだ視線で眺めるようになり、同じアジアの国々を偏見に満ちた傲慢な視線で見下ろすようになってしまっている気がします。 いつの時代でも、またどこの国でも、権力者は大衆を自分の思い通りに動かすために情報を操作し、自分に都合の良い偏見を植え付けようとするものです。
それに対抗するためには権力者のフィルターを通さない正しい情報を知り、偏見に歪められない目で世界を眺める必要があります。 我々庶民にとってそれは非常に難しいことですが、自衛隊の派遣うんぬんに関する政治家達の欺瞞に満ちた議論を聞くよりも、中近東問題に関して学者や専門家が書いた文章を読むよりも、とりあえずこの作品を観ることを強くお勧めします。(^_-)
イランの叙情派監督マジッド・マジディの珠玉の一編です。 気恥ずかしくなるくらい陳腐な表現なのであまり使いたくないのですが(^^;)、古き良き時代の日本と日本映画が持っていた素朴で健気な一途さを、物質的な豊かさと引き換えに失いつつある心の豊かさを、この作品は確かに持っています。
マジディ監督の叙情的な映像センスは実に日本的というかアジア的というか、とにかく欧米の映画からは感じられない種類のもので、感覚的にも心情的にも我々日本人にぴったりきます。 この作品を観て、同じアジアの一員でこんなにも共通する感覚と心情を持っているにもかかわらず、自分が中近東の人達のことをほとんど知らず、まるで欧米人のような傲慢な視線でその人達を見下ろしていることに気づかされ、たまらなく恥ずかしくなりました。
少なくとも僕にとっては、中近東問題専門家とか国際政治研究家とかいった人達が書いたどんな文章よりもこの作品の方がインパクトが強く、中近東の人達に対する見方が大きく変わりました。 久しぶりに、映画という世界共通の映像言語の力を再認識させられた作品です。
2002年6月30日、横浜の競技場でFIFAワールドカップの決勝戦、ブラジル対ドイツの試合が行われた約6時間前、アジアの小国ブータンで、FIFA加盟203ヵ国中202位のブータンと203位のモントセラトによる"もうひとつの決勝戦”が行なわれました。 この作品はその試合の発案から試合後までを追ったドキュメンタリーです。
この"もうひとつの決勝戦”は世界中の注目を集め、日本のマスコミでも取り上げられました。 日本のマスコミではどちらかと言えば珍記録的な扱い方をされていて、僕も多少そんな感じで受け止めていましたが、このドキュメンタリーを観て、スポーツの原点と、スポーツが国際交流に果たす役割について改めて教えられた感じで、実に爽やかな気持ちになりました。
今はちょうど甲子園の高校野球大会の最中で、大人のエゴと金にまみれた馬鹿げた大騒ぎ(区長期間中に僕自身がその渦中に巻き込まれ、一千万円以上の寄付金を無理矢理集めさせられ、40台もの応援バスを仕立てさせられちゃいましたもんね……(~o~))と、マスコミによって作り上げられたあざとい”美談”にうんざりしている時だけに、この"もうひとつの決勝戦”の清々しさは本当に一服の清涼剤でした。
またサッカーというシンプルで間口の広いスポーツが、国家や民族を軽々と越えて大きな国際性を持つにいたった理由と、日本ではメジャーな野球が世界ではわずかな国でしか行われておらず、大きな国際性を持てないでいる理由が何となく理解できた気がします。