
 第5章へ
第5章へ
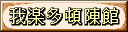
 webmaster@snap-tck.com
Copyleft (C) 2000 SNAP(Sugimoto Norio Art Production)
webmaster@snap-tck.com
Copyleft (C) 2000 SNAP(Sugimoto Norio Art Production)
さて、長春で軍のトラックに乗せられたお袋さん達軍属の家族と女子軍属は、オヤジさん達と同じように長春の駅前広場に連れて行かれ、そこで数十名から百名前後の小集団に分けられ、各小集団ごとに数名の軍人が配置されて、以後はその人達の指示に従うことになりました。 そしてそのまま1日近く待たされた後、オヤジさん達と同様に貨物列車に押し込められ、南方に向けて出発したのです。
軍属の家族と女子軍属の集団ですから、人数が多い上、指揮をしている少数の軍人以外は女性と子供と老人ばかりです。 このため、列車は2、3時間ごとに休止しながらゆっくりと進行しました。 途中、ソ連軍の襲撃に備えて、お袋さん達はトイレか病気以外は貨車から出ることを禁じられていましたし、ろくな食料もありませんでしたから、その不安と緊張は並み大抵のことではなかったそうです。 またお袋さん達の小集団には子供が何人もいましたが、乳幼児は兄貴を含めて2、3人だけでした。 このためお袋さんは、兄貴の泣き声やオムツの処理にひどく気を使ったそうです。 何しろ狭い貨車に大勢の人間が押し込められていましたし、誰もが不安と緊張で憔悴し、イライラと怒りっぽくなっていたのです。
数日後、列車は南満州の瀋陽(当時の奉天)に着きます。 お袋さん達はそこで数日間待機させられましたが、やがて8月15日となり、駅前広場に集められて天皇の詔勅放送を聞かされました。 その放送はやはり雑音が非常に多く、内容がすんなりとは理解できなかったそうですが、みんなで色々と話し合ったり、軍人に尋ねたりして、徐々に日本の敗戦を認識したということです。
その放送の後、瀋陽に集まっていた避難民は小集団ごとに独自の行動をとり始め、大きく分けてそのままそこに留まるグループと、さらに南下を続けるグループとに分裂しました。 もちろん、お袋さん達には最初から行く先も目的も知らされていませんでしたが、瀋陽までは一団となって行動していた大集団の足並みが、敗戦放送の後、にわかに乱れ始めたことを何となく察知していました。 それは各小集団を指揮している軍人達が途方に暮れたような表情で話し合っている様子からもうかがえましたし、独自の行動をとる小集団が出始めたことからも知ることができました。
後でわかったことですが、実はこの集団を指揮していた軍人達は、最初に「軍属の家族と女子軍属を早急に南部安全地帯に避難させ、できれば朝鮮半島に疎開させよ」という命令を受けたのみで、後は避難する先々で、時々刻々変化する状況に合わせて詳しい命令を受ける予定でした。 しかし長春を出発して間もなく、命令を下すはずの関東軍上層部と連絡が取れなくなり、関東軍の撤退や日本の敗戦という激しい状況の変化に対して、自分達だけの判断で行動せざるを得なくなっていたのです。
満州の一般居留民にも、またオヤジさんのような関東軍下層部の軍人や軍属にも極秘にされていましたが、戦争末期における関東軍は「無敵関東軍」と称せられた以前とは大きく変貌していました。
日本の軍部中枢は次第に悪化する戦局に応じ、日本本土を死守するために満州の存続を半分以上あきらめていたようで、関東軍の兵力をさかんに南方戦線の補強や本土決戦用に転用しました。 このため関東軍はその主力の大半を失い、それを補うために、それまでは兵役を免除されていた開拓民を手当たり次第に現地召集し、にわか兵士に仕立て上げていたのです。 兵士といっても、正式な戦闘訓練を受けていない人達ですから戦力としてはほとんど期待できませんし、兵士と一緒に多くの武器も日本本土に送り返してしまっていましたから、中には丸腰の兵士もいたそうです。
しかし開拓民から現地召集するにも限りがあり、最後には満州奥地、特にソ連との国境付近に配置されていた兵士を関東軍司令部のあった長春近辺に集め、満州中央部の兵力減少を少しでも補おうとしました。 オヤジさんが国境警備隊から長春の関東軍司令部勤務に変わったのは、こうした動きの一環でした。 その結果、ソ連軍が参戦した時点では関東軍は全盛期の半分以下の兵力に縮小していて、しかもその3分の1以上はにわか仕立ての未教育補充兵でした。 そして満州奥地から国境付近にかけてはほとんど無防備に近く、長春近辺ですら名前だけの守備隊で守られているにすぎなかったのです。 こうして、”無敵”関東軍はソ連軍に対してまともに応戦することもなく、ほとんど一夜にして壊滅状態に陥りました。
このため、ソ連の参戦を知ると日本軍の中枢部は即座に満州からの撤退を決定し、とりあえず日本領土であった朝鮮半島への避難を命じます。 その避難はまず満州国官吏とその家族、次に満州鉄道等の半官半民会社および国策会社関係者とその家族、その次に軍人軍属とその家族、最後に満州奥地の開拓団を含む一般居留民の順で行われました。 つまり、沈没しかかっている船からまず真っ先に乗務員が避難し、次に警備員、最後に一般乗客が避難したようなものですから、国家と軍に見捨てられた一般居留民の大混乱は想像するに難くありません。
この時軍部は、わずか6日後の8月15日に日本が降伏することも、1910年(明治43年)の韓国併合以来、長い間日本の支配下にあった朝鮮が日本の敗戦と同時に日本から独立することも、全く予想だにしていませんでした。 その読みの甘さと、「戦時下に於いては国家中枢機関の保護および兵員兵器の確保が優先し、戦闘行動に必要とあらば民間人を見殺しにすることもやむを得ない場合も有り得る」(ある関東軍高級将校の談話)という国家と軍部最優先の原則が、満州の一般居留民を捨て駒扱いさせ、数々の悲劇を生み出すことになります。
実際には、いち早く情報を知り得た満州国高級官吏以外の人達はほとんど同時に避難命令を受けましたが、立場上、鉄道等の公共交通機関を容易に利用できた満州鉄道や国策会社関係者は、避難活動を有利に行うことができましたし、軍人軍属とその家族達も日頃から組織的な行動に慣れていたため、比較的迅速に避難することができました。
それにひきかえ一般居留民は人数も多く、しかも組織行動に慣れていませんでしたから、どうしても避難するのに手間取ってしまいました。 中でも満州奥地の開拓団の人達は避難命令などの情報伝達に時間がかかる上、交通手段もほとんどありませんでしたので避難は困難を極めました。 しかもこういった一般居留民を組織化して指揮すべき政府機関や、彼等を護衛すべき軍隊が我先にと避難しているわけですから、大混乱に陥るのも無理はありません。 途中で指揮系統が混乱し、各小集団が独自の判断で行動せざるを得なくなっていたとはいえ、軍属の家族達と女子軍属ばかりの集団であり、しかも一応は関東軍の軍人に率いられたお袋さん達の集団は比較的恵まれていた方だと言えるでしょう。
一番大きな被害を受けたのは、当然のことながらソ連との国境付近にいた北方開拓団の人達でした。 防衛上の理由から、国境付近の守備隊はソ連に対して扇型に配置されていて、北方開拓団はその後方で開拓を行っていましたが、戦争末期には守備隊はほとんど実態のないものに成り果てていましたから、北方開拓団はソ連に対する防衛の最前線に取り残された格好になっていました。 しかもソ連軍が国境を越えて侵入してきた時、わずかに残っていた守備隊は、ソ連軍の追撃を阻止するために橋や道路を破壊し、敵に利用されるのを防ぐために停車場や官公庁の官舎などのめぼしい建物を爆破して撤退したのです。 その結果、退路を絶たれた北方開拓団は守備隊が撤退するためのスケープゴートとなったのです。
ソ連軍は”無敵”関東軍の猛抵抗を予想し、非常に勇猛果敢な部隊を最前線に揃えて侵入してきましたから、北方開拓団は言わば飢えた狼の前に投げ出されたウサギのような状態でした。 こうして多くの北方開拓団の人達がソ連軍に虐殺され、強姦され、略奪されるという悲劇が起こります。 中には女子供にいたるまで惨殺され、全滅した開拓団もありましたし、敵に辱められるよりはと、自ら総自決の道を選んだ開拓団もありました。 このようなソ連軍による蛮行は、古来より勝利軍の間で公然と行われてきた殺人、強姦、略奪勝手次第という風習に、敵愾心と恐怖心がないまぜとなって暴走したものであり、戦時下では多かれ少なかれ行われる行為です。 例えば南京陥落時における日本軍による南京大虐殺、ベトナム戦争におけるアメリカ軍による虐殺等、例を挙げれば枚挙にいとまがありません。
またソ連軍の参戦、日本の無条件降伏という混乱に乗じて、それまで日本に虐げられていた中国の民衆が各地で蜂起し、日本人に対してリンチや強姦や略奪行為を行いましたが、開拓地はその被害が特に大きいところでした。 開拓地といっても、元を正せば中国東北部で暮していた中国人達の土地を日本政府が無理矢理取り上げ、勝手に日本の開拓団に分け与えたものが多く、元の地主は自分の土地から追い出されたり、日本の開拓民の小作や下男として働かされたりしていました。 このため開拓団の人達は、直接の責任は無いとはいえ、成り行き上、満州の中国人達の恨みを買う立場にあったのです。
そのような文字どおり四面楚歌の中をかろうじて難を逃れた開拓団の人達は、ハルピンや長春といった都市を目指して、数百キロもの道のりを着のみ着のままの姿で避難しました。 それはろくな食料も持たず、荒野から荒野へ、草原から草原へ、森林を抜け、河川を渡って逃げまどう、死に物狂いの逃避行でした。 集団からの落伍はそのまま死を意味しましたが、それがわかっていながら他の者は歩き続けるしかないのです。
このような逃避行では、体力のない子供と老人がたいてい最初に落伍します。 どの集団でも疲労と飢えで母親の乳が出なくなり、幼児は次々と餓死していき、気がつくと背中で冷たい骸となっているのです。 それら幼児の亡骸の多くは埋葬されることもなく、そのまま道端に放置されていきましたが、中には餓死して腐臭激しい我が子の亡骸をかたくなに手放そうとしない母親もいたそうです。 また我が子の苦しみを短くするために、あるいは自分の子供の泣き声が他の人達を危険にさらすのをはばかって、自ら幼い命を縮める母親もいましたし、どうしても我が子を手にかけられず、親に代わって集団の引率者が子供の命を絶たねばならないこともありました。 さらには足手まといとなった子供や老人を置き去りにした集団や、やむなく殺してしまった集団まであったといいます。
こうしてやっとの思いでハルピンや長春にたどり着いても、そこの日本人はすでにほとんどが避難した後で、さらに南部の瀋陽まで過酷な逃避行を続けることになります。 そして瀋陽までたどり着いた集団は、避難距離に反比例して生存率が低くなり、北方の開拓団ではその1割が生き残っていればいい方でした。 最終的には、満州開拓団27万人のうち約3分の1にあたる8万人もの人々が死亡あるいは行方不明となり、満州における日本人犠牲者の大半を占める結果となります。
そもそも満州開拓団とは、当時の日本国内の人口・食糧問題の解決のために満州に送り出された貧しい小作農民とその家族達で、ある意味では、国家の政策の犠牲となって中国大陸に追い出された棄民であると言うことができます。 そしてこの人達は、満州滅亡時にまたしても国家の犠牲となって中国大陸に見捨てられたのです。 その混乱のさなかに孤児となったり、避難中に置き去りにされた子供達のうち、かろうじて生き残り、心ある中国人によって養育された人達がいわゆる「中国残留孤児」です。 この中国残留孤児達も長い間日本政府から放置されたままで、民間人の地道な努力により、敗戦後40年近くたって、その中の運の良い一部の人達がやっと祖国日本の土を踏めたことは記憶に新しいところです。
そして侵略戦争を起こした張本人であり、一般居留民を犠牲にして真っ先に逃げた官吏や軍人が、国家から補償と恩給を貰ったのに対して、ある意味で侵略戦争の犠牲者でもある開拓団をはじめとする多くの一般居留民が、彼等の犠牲となって命を落とし、かろうじて生き延びた者も、何の補償も貰えず戦後の混乱の中で生きることに必死になっていました。
このように、戦争末期における徹底抗戦・本土決戦・一億総玉砕から一転して無条件降伏という日本政府の選択の中で、北方侵略政策に基づいて満州に進出した人々は本土決戦のための悲運な捨て駒になったと言えます。 同様な意味で、南方侵略政策に基づいて東南アジアに進出した人々は、徹底抗戦の手本として悲壮な自決の道を選び、沖縄の人々は一億総玉砕の先駆けとして悲惨な犠牲者になったと言えるかもしれません。 こういった事実は国家というものの本質的な一面、すなわち最下層の庶民の犠牲の上に立って、ただ国家という組織それ自体を存続させることのみを唯一の目的とした非人間的な存在という一面を露呈する、象徴的な出来事と言えるでしょう。
全てが純粋に善意だけに基づくわけではなく、複雑な事情と思惑が背景にありますが、中国残留孤児の存在とその人達を快く日本に里帰りさせたところに、中国人の懐の深さを感じます。 もし逆の立場だったとしたら、我々日本人に中国人と同じことができただろうかと考えますと、少々悲観的な気持ちにならざるを得ません。
この非人間的な性質は、国家という組織に限らず、会社など広く組織というもの一般が持っている本質的な特徴であるような気がします。 この性質ゆえに、往々にして組織はその構成要素である個人の意思を単純に総合したものとは全く別の意思を持つことがあります。 しかしそういった個人の意思と集団の意思のズレは、他でもない個人の本音と建前のズレ、そして良心と利己心のズレを反映したものであり、人間の持つこうした本質的な矛盾がまた、組織の持つ非人間性や矛盾の源となっているように思われます。