
 第8章へ
第8章へ
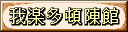
 webmaster@snap-tck.com
Copyleft (C) 2000 SNAP(Sugimoto Norio Art Production)
webmaster@snap-tck.com
Copyleft (C) 2000 SNAP(Sugimoto Norio Art Production)
収容所の生活がまだ極限まで追い詰められていない頃、オヤジさんは演芸団のようなものを組織して、慰問のために賑町の収容所の家々を訪問して回ったことがあります。 オヤジさんは子供の頃から音楽が好きで、特に色々な楽器を演奏することが得意でしたので、学校でも軍隊でも演芸会の常連でした。 賑町に収容されてからも、何とか楽器を作ろうと思い、使役先から大きな丸いブリキ缶をもらってきてそれを適当な大きさに切り、木の棹を取り付けて針金を張り、ギターのできそこないのようなおかしな楽器を作りました。 そして夜になると、それをかき鳴らしながら、同じ部屋の人達と一緒に知っている限りの歌を片っ端から歌って(と言うよりも、怒鳴ったと言った方が適当だったそうですが…(^^;))楽しんだのです。
するとそのうちに、そのことを知ったあちこちの部屋の人達がオヤジさんに来て欲しいと頼みに来ましたので、オヤジさんはその楽器を持って、毎夜、色々な部屋に行ってはそこの人達と一緒に合唱を楽しみました。 そうして色々な部屋を回ってみると、あちこちに歌や踊り、講談、手品などの上手な人がいたので、そういった芸達者達を集めて演芸団を組織することにしました。 そしてそのシロウト演芸団を引き連れて、避難団が収容されている賑町の家々を慰問して回りました。
その後、日本に帰ってからもオヤジさんは色々な楽器を手にし、死ぬ間際まで身辺から楽器を手放したことはありませんでしたが、オヤジさんの心の大きな慰めとなった点においても、他の人を心から喜ばせた点においても、そのできそこないの楽器に優るものはなかったといいます。
さて、男狩りの結果、使役に出て食料をもらってくる働き手が減ってしまったので、収容所の食糧事情はますます悪くなり、誰もが多かれ少なかれ栄養失調状態になりました。 また収容所には風呂などという贅沢なものはありませんでしたし、衣服も着たきりスズメでしたので、みんな垢だらけで衣服もボロボロでした。 その結果、身体中にシラミがわき、朝百匹ほど取っても、夜にはまた百匹ほど取らなければならないといった状態で、シラミ取りを日課にしているような有り様でした。
こういった不衛生極まりない状態ですと、必ずと言ってよいほど起こるのが疫病の発生です。 そしてこの時も例外ではありませんでした。 ある家から発疹チフスが発生したのを発端として、たちまちのうちに収容所全体に大流行したのです。 収容所に医者はひとりもおらず、医薬品なども全くありませんでしたから、手の施しようもなく、大勢の人達がチフスにかかりそのままばたばたと死んでいきました。 当初は賑町全体で四千人ほどの避難民が収容されていたのですが、このチフスの大流行によって、最終的には半数の二千人近くが命を落とす結果となります。
毎日毎日、沢山の人が死んでいきますので、人の死には無感覚になってしまい、最初は遺体を丁寧に埋葬していたのが、やがて死にそうな病人がいると、その周囲の誰かが「死んだらその服をくださいね?」と約束を取り付け、その人が死ぬと遺体の衣服をはいで埋葬するようになりました。 そしてこういった裸の遺体が、毎朝、収容所の入り口近くに集められ、担当の人が近くの空き地に埋めに行くのが日課となったのです。 このように人の死を眼前にしていながら、オヤジさんもお袋さんも自分が死ぬなどということはこれっぽっちも考えなかったといいますから、やはり若くて恐いもの知らずだったということでしょうか。 ところがその恐いもの知らずのオヤジさんも、大流行の最盛期についにチフスに感染してしまい、40度以上の高熱が数日間続きとうとう意識を失ってしまったのです。
オヤジさんがぼんやりと意識を取り戻した時、最初は目の前が真っ暗で何も見えませんでした。 やがて意識がはっきりしてくると、それは何かが顔の上に乗っているためだと気付き、それを取り去ろうとするのですが、手がやたらと重くてなかなか動きません。 しばらくしてやっと手を動かしてそれを取ってみると、それは白い布切れで、天井に小さな裸電球がぽつんと灯っているのが見えました。 そのうちにだんだんと目が慣れてきたので、重い首を左右に動かして周囲を見ると、そこは古い物置のような部屋で、どういうわけか白い布切れを顔に被った人達がたくさん寝ています。
「変な人達だなァ…?」と思いながら起き上がろうとするのですが、全身がひどくだるくてどうしても起き上がれません。 仕方がないのでしばらくじっとしてあれこれと考えていると、やっと自分が発疹チフスで倒れたことを思い出し、そのとたんに急に激しい寒さに襲われて、全身がガクガクと震えだし奥歯がカチカチと鳴り出しました。 こんな所でウロウロしていたら大変だと思い、オヤジさんは全身の力を振り絞って出口と思われる方向に少しずつ少しずつ這って行きました。 そして(実際には数分間だったのでしょうが)何時間も過ぎたと思われた頃、入り口の戸が開いて誰かが顔を出したので、その顔に向かって必死になって叫ぼうとしましたが、どうしても声が出ず、そのまままたしても気を失ってしまいました。
次にオヤジさんが意識を取り戻すと、目の前にソ連軍の軍服を着た女性の顔があり、強い薬品の匂いが鼻をつきました。 驚いて周囲を見回すと、今度は清潔な白いシーツの寝台に寝かされていて、前よりも身体がずっと楽になっています。 そしてそこはソ連軍の野戦病院(元の朝鮮道立病院)で、ソ連軍の軍服を着た女性はそこの軍医であり、さっきまでオヤジさんがいた部屋はその病院の死体安置所であることを知らされました。 こうしてオヤジさんは、まさしく死の淵から生き返ったのです。
オヤジさんが死の一歩手前を彷徨していた頃、お袋さんの方も大きな危機に直面していました。 発疹チフスはソ連でも法定伝染病でしたので、ソ連軍も手をこまねいて傍観しているわけにはいかず、オヤジさんがチフスにかかる少し前から感染者を病院に収容し、外部から隔離するようになります。 このためオヤジさんが高熱で倒れて、チフスに感染したらしいとわかると、ソ連軍がやってきて収容所から連れて行ってしまったのです。
そしてそれから間もなく、残されたお袋さんのところに病院に収容されたオヤジさんからという手紙が2通届けられました。 その手紙は多少乱れてはいるものの確かにオヤジさんの筆跡で、お袋さん宛のものには、
「長い間世話になったが、何もしてやることができなくてすまない。 竜夫を頼む。 日本の皆様によろしく」
という意味のことが書いてあり、兄貴宛のもには、
「父は御国のために命を捧げた。 お前はお母さんの言う事をよく守って、御国のために役に立つ人間になれ」
という意味のことが書いてありました。
この遺言状を読んだお袋さんはさすがにびっくりしましたが、まだオヤジさんが死んだと決まったわけではありませんし、お袋さんにはどうすることもできませんので、とりあえず兄貴と二人で生き延びるのに専念することにしました。 何しろオヤジさんの使役から得られる食糧がなくなったわけですから、何とかして自分と兄貴の食料を手に入れなければなりません。
その頃、女性が食料を手に入れるには、主に3つの方法がありました。 ひとつは使役に出て食料を手に入れる方法ですが、これは若くて元気な女性しか勤まらず、栄養失調とチフスの流行で実行する人が次第に減っていました。 もうひとつは、自分の身体と引き換えにソ連軍や韓国赤衛軍の兵士から食料を手に入れる昔ながらの方法です。 最初のうちはソ連軍の兵士にいたずらされるのが嫌で、ほとんどの女性は髪を短く切り、わざと顔を汚して男に化けていたのですが、ソ連軍の兵士が黒パンなどをくれるので、そのうちに一部の女性達は女に戻り、自ら進んでソ連軍の兵舎などに遊びに行くようになっていたのです。
最後のひとつは、韓国人の家に物乞いに行ったり、残飯を漁ってきたりする方法です。 お袋さんは兄貴を連れていましたので使役にはあまり行けず、かといって自らソ連軍の兵舎に身を売りに行くことはしたくありませんでしたので、仲の良い友達と連れ立って近くの韓国人の食堂街に行き、残飯漁りをすることにしました。 日本人は長い間朝鮮人を蔑視し、苛めてきましたので、当時の朝鮮は反日感情が非常に強く、物乞いに行くにしても残飯を漁るにしても女性ひとりでは危険でしたから、たいてい数名のグループで行動するようにしていました。 もちろん中には親切な朝鮮人もいましたが、日本人に親切にすると村八分のようにされる風潮がありましたので、そういった人達も人目を忍んでこっそりと物や残飯をくれるのが常でした。
お袋さん達が残飯を漁りに行ったのは、主に収容所の近くにあった食堂街でした。 そこには色々な屋台も出ていましたので、残飯漁りに好都合だったからです。 数名のグループでその食堂街に行くと、見張り役と残飯漁り役とに別れ、屋台の主人や客の目を盗んで、客の食べ残しやごみ箱に捨てられた残飯をこっそりとかすめ取るのです。 運悪く店の主人に見つかると、たいていは殴られたり乱暴に追い払われたりしましたが、中にはわざと知らないふりをしてくれる親切な人もいたそうです。
こうしてお袋さんは何とか飢えをしのいでいましたが、そのうちに運の悪いことに腹に虫がわき、熱を出して寝込んでしまいました。 とにかく不衛生極まりない状態でしたから、避難民はみんな腹に虫がわいていて、多かれ少なかれ腹痛と発熱に悩まされていたのです。 母乳はとうに出なくなっていた上、頼みの綱の残飯も手に入りませんから、兄貴はみるみる衰弱してやせ細り、目玉と下腹だけが異様に飛び出した重度の栄養失調となって(このような状態を昔の人は「餓鬼」として表現しました)、いつ死んでもおかしくない状態でした。
この時、お袋さんと仲の良かったSさんという若い女子軍属の人が、お袋さんの状態を見かねて、自分が使役で手に入れた食べ物をお袋さんと兄貴に分けてくれ、何くれとなく親切に面倒を見てくれました。 そのおかげで兄貴は危ういところを助かり、お袋さんも何とか危機を脱することができました。
一昨年(1994年)の秋、急性肺炎にかかって入院した時も、オヤジさんは愛用のレキントギター(ラテン用の小さなギター)を病院に持ち込み、いつもベッドの脇に置いていました。 入院して1ヶ月ほどたった頃、オヤジさんの容態が急変したという連絡を受けた僕が駆けつけると、オヤジさんはベッド脇のレキントギターを指差し、
「あれは典夫(僕の本名)にやる。 まあ、形見みたいなもんだな……」
と言って、病気やつれした顔を微かにほころばせました。 それから数日後、オヤジさんは静かに息を引きとりました。 生涯、音楽と楽器を愛してやまなかった、いかにもオヤジさんらしい最後でした。
日本の敗戦以前は、朝鮮人や中国人に親切にする日本人は、異端として周囲の日本人からつまはじきにされる傾向がありました。 何しろ朝鮮人や中国人が米のご飯を食べているところを日本人に見つかっただけで、「お前らはコーリャンで十分だ!」と殴る蹴るの暴行を受け、それを止めようとした心ある日本人も同じように暴行を受けたほどです。
この命の恩人ともいえるSさんとは、日本に帰国すると同時にろくにお礼も言わないまま別れ別れになってしまいました。 そのため生活に余裕ができてから、一言お礼を言いたいと色々と手をつくして探したのですが、なかなか見つかりませんでした。 ところが帰国から40年以上もたって、ひょんなことからそのSさんが一宮市に住んでいることがわかり、早速連絡を取り、兄貴を連れて感激の再会を果たしました。 こうしてお袋さんは、40年間心に抱いていた感謝の気持ちをようやく伝えることができたのです。