
 第2章へ
第2章へ
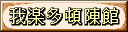
 webmaster@snap-tck.com
Copyleft (C) 2000 SNAP(Sugimoto Norio Art Production)
webmaster@snap-tck.com
Copyleft (C) 2000 SNAP(Sugimoto Norio Art Production)
「……てなわけで、あたしが高校時代の親友、雪ちゃんにたまたま二人を紹介したら、雪ちゃんと荻須君が意気投合しちゃって、恋人同士になったってすればいーわよ」
とミミ嬢が気楽そうに言った。 彼女は雪子さんとも僕等とも親しいためか、緊張ぎみな僕や伴ちゃんにひきかえ、ゆったりとリラックスして楽しそうだ。
僕はミミ嬢のやたらと楽観的な設定を、もう少し説得力のあるものにしたくて言ってみた。
「意気投合はいーけど、持田さんとどーゆーふうに意気投合したらいーのかなあ」
「どーゆーふうにって、どーゆーこと?」
「例えば共通の趣味とか話題とか、何かそんなもんいるんじゃないかなあ……」
共通の趣味なんてまず無理だろうとは思いつつ、一応、雪子さんに尋ねてみた。
「持田さん、何か趣味あります?」
「趣味ですか? そうですねえ、テニスかしら……」
「テニス! ……ですか」
「高校の時、ミミちゃんと同じテニス部だったんですよ。
ミミちゃんみたいに強くなかったですけどね」
ミミ嬢にチラッと視線を送り、雪子さんは昔を懐かしむような表情でニッコリと笑った。 育ちのせいか、こんな時だってのにおっとりしていて緊迫感のかけらもない。
「そうですか、テニスですか……。
そりゃダメだ、僕、テニスなんてやったことないですもんねぇ。
他に何かありません?」
「なーに言ってんの、恋に趣味もへったくれもあるもんですか。
フィーリングよ、フィーリング!」
と横からミミ嬢が口を出し、
「目と目が合って、『これだっ、この人だーっ!』て感じればいーのよ」
彼女ときたら、まるで二流の青春ドラマみたいに安直なストーリー展開にしたいらしい。
「でもねー、共通の話題もないのに、こんなに早く恋人同士になるなんてさあ、何となく不自然じゃないかなあ……」
僕は何とか論理的なストーリー展開にすべく頑張った。
「僕等だって、大学に入ってから知り合ったんだから、まだそれほど時間がたってないのにさあ」
「時間も歳の差も関係ないのよ、恋には。
細かいことはどーだっていーから、手っとり早く、パーッと決めちゃいましょーよ、パーッと!」
可愛い顔に似合わず、ミミ嬢には案外おっちょこちょいでそそっかしいところがあって、かつての憧れの美少女スター「操ちゃん」の清純可憐なイメージがガタガタと崩れてしまう。 これは、この話を持ちかけられてから彼女と親しくしゃべることが何かと多くなって、とみに気づいたことだった。
この時、今までポケーッとしていてほとんど口をきかなかった伴ちゃんが、ボソッと言った。
「ぼ、僕も、お、小山内さんに賛成だよ、友規」
伴ちゃんは普段から口数が少なく、人が話をしているのをポケーッとしながら聞いていることが多いので、たまに口を開くと妙にみんなの注目を集めるところがある。
「人と人が理解し合えるってのは、そりゃあ、時間も少しは関係するけど、何てったらいいのかな、人柄ってのか、気持ちってのか……」
伴ちゃんは独特のはにかみがちな人懐っこい笑顔を浮かべて、
「うまく言えないんだけど、一回会っただけでも、ああ、この人は、自分と同じような人間なんだなって、何となくわかるもん。 友規なんか、大学入って最初見た時、すぐわかったよ」
僕は胸の奥から暖かいものがこみあげてきて、思わず言葉に詰まってしまった。 実は、僕が伴ちゃんを初めて見た時も全く同じことを思ったんだ。 人間というのは自分と同じような人間はお互いにすぐそれとわかるもんらしく、大学に入って周囲を見回した時にも、ああ、こいつは仲間らしいとすぐピンと来た奴と、まるで顔が無いみたいにほとんど目に入らなかった奴とがいた。 そして仲間と感じた奴と話してみると、ほとんどの場合はやっぱり気が合う仲間となり、そうでない奴とはいくら話していてもあまり理解することができないでいる。 人と人との関係ってのは、確かに付き合った時間の長い短いだけじゃないようだ。
「わかってるー、さっすが伴ちゃん、よーくわかってるーっ! そーよ、そーなのよ、要はハートよ、ここの問題よね!」
ミミ嬢、大きくうなずきながら自分の胸をポンとたたいた。 その「我が意を得たり!」といった様子を見て、意外と彼女には人を見る目があるのかもしれない、僕と伴ちゃんに白羽の矢を立てたのは、僕が伴ちゃんを選び、伴ちゃんが僕を選んだのと同じような理由によるものなのかもしれない、なんて(うぬぼれかもしれないけど)思っちゃったりなんかした。
「あたしは、伴ちゃん? あたしは、最初見た時どー感じた? すぐわかった?」
と、ミミ嬢はそのキュートな茶目っぽい目を伴ちゃんに向けた。 ミミ嬢のように日本全国誰でもが認めるカワイコちゃんが、伴ちゃんのように、おそらく日本全国誰でもが認めるカッコワルイコ君にこんな質問をするのは、たいてい相手をからかっているのか、それとも自分の美しさを認めさせたいという思いからが多いけど、この時のミミ嬢にはそんな感じはこれっぽっちもなく、むしろ冗談めかして笑っている顔とは裏腹に、気のせいかもしれないけど、瞳の奥に何となく不安げな真剣なものを感じて、「おや?」と思った。
「あ、あの、それは、その、小山内さんのこと、今までは、あんまり、しっかり見れなかったもんで、つまり、その……」
「感じなかったのね、やっぱし……」
今度は気のせいばかりじゃなく、確かにミミ嬢はシュンとしてしまったらしい。 強いて作ったような笑顔が、妙に弱々しかった。
「そうよねー、あたし、第一印象いいって言われたこと、あんましないもんねー」
「そ、そうじゃないよ!」
伴ちゃんには珍しく強い口調だった。 でもすぐ小声になると、いつものように早口のボソボソとした調子で、
「つ、つまり、その、もっとしっかり見て、もっと話して、つまり、その、もっと色々知りたかったんだけど、ぼ、僕、女の子としゃべるの、苦手なもんで……」
「あら、だったら遠慮せずに、じゃんじゃん話しかけてくれたら良かったのにー。
伴ちゃんって、何だかあたしのこと避けてたみたいなんだもんね」
「そ、そんなことないよ!
つまり、その、小山内さんを最初に見た時、何となく、つまり、その、何となくだけど、友達になれそうな気がしたんだけど、でも、僕、女の子としゃべるの、苦手なもんで……」
何事にも一生懸命でかわいそうなほど一途な伴ちゃんは、口べたな、それでいて真実味溢れる口調と誠実そのものの態度とで、相手の心を引きつけてやまないところがある。 そして口数こそ少ないけれど、それだけに口にする言葉はまっすぐ真理を貫いていることが多い。 そんなところが、みんなから「ミスター理学部」と敬愛されているゆえんなのだ。
「ほんと? ほんとーに、そう思ってくれてたの?」
心なしか曇っていたミミ嬢の顔が、とたんにパッと明るく輝いた。
「あのね、ほんとゆーとね、あたしも、ずっと前から、伴ちゃん達となら、何となく気が合うかも知れないなって思ってたんだ、実は。 でもさあー、伴ちゃん達ったら、あたしがいっくら話しかけても、ぜーんぜん振り向いてもくれないんだもんねー」
口をとがらせ、そのくせ目は嬉しそうに笑わせながらミミ嬢はすねたように言った。
そういえば、ミミ嬢に言われて今初めて気がついたことだけど、入学以来、彼女は何かと僕等に話しかけてくることが多かったような気がする。 僕等のクラスには五人の女の子がいて、まあ理学部を選ぶような女の子だからやっぱり多少変わっていて、男や女をあまり意識せずに話せるところがあるけど、それでも伴ちゃんに話しかけるというのは、初めのうちはためらいがあったようだった。 ましてフツーの女の子なんて、話しかけることはおろか伴ちゃんの周囲3メートル以内には近寄ろうともしない。 それなのにミミ嬢は誰よりも先に伴ちゃんに話しかけ、他の女の子から驚異の目で見られたもんだった。
僕は、彼女が誰彼となく愛敬を振りまくのは、かつての職業柄、むしろ当然と思っていたんだけど、よく考えてみると彼女が自分から男の子に話しかけたことはあまりなく、たいてい野郎どもの方からニタニタと話しかけていったんだった。 しかもそういう時の彼女は、愛敬どころか何となく迷惑そうな顔でぶっきらぼうな生返事をしていることが多く、僕等と話す時とは別人のようだった。
「い、いや、それはつまり、その、小山内さんって、男の子に話しかけられると、何となく、迷惑そうだったもんで、ついその……」
と、伴ちゃんもそのことに気付いていたようだ。
「あら、そんなことないわよー。 そりゃあ、初対面の男の子にいきなり馴れ馴れしく話しかけられたりしたら、ちったあ迷惑そーな顔したかもしんないけど。 あたし、どっちかっちゅーと人見知りするタチだし……」
全く、「人見知りするタチ」が聞いてあきれるよ。 人見知りするタチの女の子が、まだたいして親しくもない野郎二人におかしな相談をもちかけて、はるばるこんなとこまで連れてくるかねぇ……と思ったけど、さすがに口にはしなかった。
「人見知りするタチとはとても言えないけど、昔からそうなんですよ、ミミちゃんて」
雪子さんが、まるで妹を見るような優しい視線でミミ嬢を包み込みながら言った。
「自分から友達になろうとすると、『芸能人の八方美人』だって思われるし、相手から近付いてくるとかえって警戒してしまうもんだから、『お高くとまってる』なんて思われたりして……」
「損な性格なんですねー、あたしって。
あぁ、何て不幸な星の下に生まれたんでしょ!」
ミミ嬢はまるでマッチ売りの少女でも演じているように、大げさな身振りをして芝居がかった口調で嘆いた。
「高校ん時なんて、クラブやってても、雪ちゃんばっかもてて、あたしなんてボーイフレンドひとりいなかったのよ。
こんなカワユイ女の子をほっとくなんて、みんな見る目がないんだからー」
「何言ってるの、ウソばっかり!」
雪子さんは、何とか言ってやって下さいよ、と言わんばかりの表情で僕等を見て、
「あたしに近付いてくる男の子といったら、たいていミミちゃん目当てで、『サインをもらってくれ』って頼まれるか、『ラブレターを渡してくれ』って頼まれるか、どっちかだったんですよ」
大学の友達の前ではスター時代の話題をできるだけ避けていて、『操ちゃん』なんて呼びかけられても体良く無視しているミミ嬢だけど、雪子さんの話は安心しきった顔つきで聞いている。
「それをミミちゃんったら、色紙を真黒に塗り潰したり、ラブレターを破り捨てたり、まるで男の子を寄せ付けないんですよ」
「そーじゃないんだってばァ!」
とミミ嬢はあわてたように、
「寄せ付けなかったわけじゃないのよ。
だってさぁー、人に頼むなんて、男らしくないんだもんね。
男なら、堂々と面と向かって言えばいーのよねー」
「面と向かって『サイン下さい』って言った子に、あなた、どうしたんだったかしらねェ?」
ミミ嬢が何か言いたげだったけど、すかさず僕が突っ込みを入れた。
「どうしたんです?」
「ごく普通の字で、名札みたいに『2年3組小山内ミミ』って書いたんですよ!」
「だってさぁー、あれはさー、仕事で使ってたサインはマネージャーの人が考えたエーギョー用のサインで、学校で使うサインてったら、とーぜんあーなるわよ」
ミミ嬢は、さも当然といった顔つきだ。 彼女ならやりかねないと思って僕は大笑いをしたけど、伴ちゃんは何がなんやらわからないってな顔でボーッとしている。 ま、当然でしょう、スターってもんすらよく知らない彼に、スターのサインがどういう価値を持つもんだか理解できるわけないよね。
「学校じゃなくて仕事中に頼まれれば、あたしだって喜んでサインしたよ、ニッコリとエーギョー用の微笑み浮かべてさ」
と言いながら、ミミ嬢は懐かしい「操ちゃんスマイル」を本当に浮かべて見せた。 その笑顔は、まぎれもなくかつて僕が夢中になった操ちゃんの清純可憐な笑顔そのものだった。 でも不思議なことに、クラスメート「小山内ミミ」嬢を知った今となっては、その笑顔の裏側に、「南井操」の仮面を嫌がり、自ら茶化しているミミ嬢の素顔が透いて見えるんだ。 そんな様子を見ていたら、スター時代の話題をつとめて避けているミミ嬢の気持ちが、何となくだけどちょっぴり理解できたような気がした。
「ところでねー、あたしたちこれから共犯なんだし、恋人同士なんだから……」
と、本来の目的を思い出したのか、お茶目な地顔に戻ったミミ嬢がやっと作戦会議らしいことを言い出した。
「空々しく、『小山内さん』、『荻須君』なんて呼び合うのも変よねー。
それらしく、馴れ馴れしく呼び合うことにしよーよ」
「そうね、それがいいわね。
あたしたちは、『ミミちゃん』と『雪ちゃん』って呼び合ってるから、そう呼んでもらえばいいですけど……」
そう言う雪子さんと視線を交わしてうなずき合うと、ミミ嬢は僕等の方を向いた。
「伴ちゃん、荻須君、なんて呼ばれたい?」
ミミ嬢に尋ねられた僕は、まず簡単な方から片づけてしまおうと伴ちゃんを振り返った。
「伴ちゃんのことは誰でも『伴ちゃん』って呼ぶから、それでいいよな?」
伴ちゃんはコックリとうなずいた。 伴ちゃんのことを本名で呼ぶ人はほとんどいないし、呼ばれた本人がピンと来ずにキョトンとしている時さえある。
「よしよし。
で、僕は、どうすりゃいーかなあ……」
「『友規』って名前なんだから、『トモちゃん』じゃどう?」
と、ミミ嬢はまるで女友達を呼ぶような言い方だ。
「トモちゃん!? なんか女の子みたいだなあー。
『友規』でいいよ、友達みんな、そー呼ぶし」
「じゃあ、『友規君』ね。恋人の雪ちゃんは?
それっぽく『友規』って呼び捨てにする?」
「ジョ、ジョーダンじゃないよ!
そんなふーに呼ばれたら、本当の恋人だって気持ち悪くて背中がゾッとするね。
『友規君』でいいよ、『友規君』」
「じゃ、これで決まり! 雪ちゃん、ミミちゃん、伴ちゃん、それに友規君」
ミミ嬢はみんなの顔をぐるりと見回すと、いたずらっぽくニコリとして、
「一度、それらしく呼ぶ練習してみよーか?」
そして僕に目をとめると、
「友規君、恋人の雪ちゃん呼んでみて」
などと恐ろしいことを言い出した。
「エッ!?
……い、いーよ、まだ。
そん時になりゃー、呼べるよ」
「なーに言ってんの、練習もせずにできるわけないじゃない。
ほら、ガタガタ言ってないで、ちゃんとやるの!
ホラッ!」
「じゃ、じゃあ、ユ、ユキちゃん。……これでいい?」
「あたしに向かって、『ユキちゃん』つってどーすんの!?
雪ちゃんに向かって言わなきゃだめよ」
「そ、そうだね。じゃあ……」
僕はしぶしぶ雪子さんの方を向いた。 彼女は必死になって笑いをこらえている。
「持田さん、いいですか、いきますよ? ユ、ユキちゃん。……これではどう?」
振り向いてミミ嬢の顔色をうかがうと、彼女はまだ気に入らないらしく、
「何よ、その『持田さん、いいですか、いきますよ?』ってのは。
彼女の恋人なんだから、オドオドしないで、自信持ってはっきり呼びなさいよー」
「ユキちゃんっ!
……これでは?」
「ケンカ売ってんじゃないのよ。
恋人らしく、こう、優しく呼んであげなくちゃー」
「ユーキちゃあーん。……こんなもんでいーだろ?」
「それじゃー、まるで幼稚園のおトモダチよ!」
ミミ嬢、なかなか手厳しい。 彼女は昔やってたからいいだろうけど、僕みたいなシロウトに急に恋人役をやれって言ったって、おいそれとできるもんじゃない。 しかも相手は今日初めて会った人ときてる、うまくやれってのがどだい無理な注文ってもんだ。 雪子さんは涙を流して笑っているし、伴ちゃんときたら腹をかかえて苦しそうに大笑いしている。 キショーメ、友達がいのないヤツだ!
それから何回もやり直しさせられて、やっとミミ鬼監督のOKをもらった時には、僕は汗グッショリになっていた。
「ま、ちょっとはらしくなったから、いーでしょー、それくらいで」
ミミ嬢、今度は伴ちゃんに視線を移し、
「次、伴ちゃんの番!」
「イッ!?」
突然オハチが回ってきて、伴ちゃん、いっぺんに笑いが止まってしまった。
「『イッ!?』じゃないわよ。 伴ちゃんは、恋人じゃなくって、友達みたいに呼ぶのよ。 ほら、『雪ちゃん』は?」
伴ちゃんは、真赤になって目を白黒させながら、口をパクパクやっている。 でも、努力も空しくその口から声は出てこない。
「ホラッ、どーしたの?
『雪ちゃん』って!」
「ゆ、ゆ、ゆ、ゆ……」
「あのねー、『ゆ、ゆ』って、おフロ屋でサンスケ呼んでんじゃないのよー」
「……ミ、ミミちゃん、ま、待って、待って!
これ以上笑ったら、死んじゃうわよ、あたし」
『雪ちゃん』が涙を拭き拭き、笑いむせびながら言った。
「四条さん、いえ、伴ちゃんは、あたし呼ぶこと、そーないでしょーから、許してあげたら?」
彼女はあっさり友達のように「伴ちゃん」と言えている。 本当に、いざとなったら女の方がよっぽど度胸があるというもんだ。
「そーねー……。 ま、いいか、純情な伴ちゃんには、ちょっくら無理な注文かもね」
その言葉を聞き、伴ちゃんがホッとして大きく深呼吸をしている様子は、死刑執行直前になって、突然、無罪放免になった囚人のようだった。
「でも、恋人の、あたしを呼ばないわけにはいかないわよォ。 友規君は、とーぜん友達みたいに呼べるでしょ?」
ミミ嬢がこっちに目を向けたので、僕は我ながらスムーズに返事をした。
「うん、そろそろ、そー呼ぼうかなって思ってたからね、ミミちゃん」
「OK、カーンペキ!
……伴ちゃんは?」
ミミ嬢に見つめられ、伴ちゃんはまたしても死刑囚の顔になった。
「恋人らしく、優しく呼ぶのよ。
簡単でしょ?
ほら、呼んでみて……」
「ミ、ミ、ミ、ミ……」
「セミねー、まるで。
ホラッ、男らしく、ポイッと言っちゃいなさいよ!」
「ミ、ミミ、ミミ……」
「そーねえ、そーゆーふうに、呼び捨てにしてくれてもステキね、恋人っぽくて」
「……ちゃん」
「『チャン』って、子連れ狼か、あたしはァ!?」
ミミ嬢、やれやれといったように肩をすくめ、
「もおー、やんなっちゃう! こんなことで、かの美少女スター南井操が監督するこの青春ドラマ、ほんとにクランクインできるのかしら……!?」