
 第3章へ
第3章へ
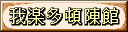
 webmaster@snap-tck.com
Copyleft (C) 2000 SNAP(Sugimoto Norio Art Production)
webmaster@snap-tck.com
Copyleft (C) 2000 SNAP(Sugimoto Norio Art Production)
「ほんとに久しぶりですよ、あのコがあんなふうにはしゃいでいるのを見るのは……」
雪子さんがしみじみとした口調で、独言のようにポツリと言った。 砂浜に残された僕と雪子さんは、海の中ではしゃぎまわっているミミちゃんと、戸惑いがちに彼女に引っ張り回されている伴ちゃんをぼんやりと眺めていたんだ。
「え?」
雪子さんの言葉が理解できず、僕は思わず雪子さんを振り返った。
「久しぶりって、それ、どーゆーことです?」
雪子さんは口元に微かな笑みを浮かべると、僕の質問をそらすように、その笑みを海の中のミミちゃん達に向けた。 ややあって、二人を眺めるその目にどこかしら遠い色を漂わせながら、
「ミミちゃんね、あれで変に意地っ張りなところがあって、弱いところは見せようとしないんですけどね、本当は寂しがり屋で、けっこう純情なんですよ」
と思い出話をするような口調で、一見、無関係に思える話を始めた。
「ええ、わかるような気がします、何となくですけど……」
「荻須さんなら、わかってくれていると思ってました。
あのコ、大学に入る前、ひどく人間不信になっちゃいましてねえ」
「人間不信?」
「ええ、そりゃあもうひどいもんでしたわよ、かわいそうなくらい落ち込んじゃって……」
「どーしてなんですか、一体?
今のミミちゃん見てると、信じられませんけどねー」
「これ、ほんとは内緒なんですけどね、荻須さんなら大丈夫ですわよね、話しても」
ミミちゃんから僕に視線を戻すと、雪子さんは目を笑わせながら、内緒話をするような調子で言った。
「いーんですよ、別に。
誰だって、人に知られたくない事ってありますから……」
「もう、あのコも十分回復してますし、それに知っておいて欲しい気もしますし……」
それから声を落とし、表情のない口調でポツリと言った。
「ミミちゃん、高校の時、失恋したんですよ、実は」
「失恋!?
ミミちゃんがですかァ!?
うっそでしょー、そんな……」
「ほんとなんですよ、それもひどいのを……」
「ヘえー、とても信じられませんねー、そんなこと。
ミミちゃんに失恋した男なら、いっくらでも知ってますけどねー、はは……」
僕が冗談っぽく笑うと、雪子さんは悲しげな微笑みを浮かべて、
「あたしも詳しいことは知らないんですけどね、ミミちゃんが芸能人だというんで、色々と変な噂をされたのが失恋の原因らしいんですよ」
「変な噂?」
「もともと、ミミちゃんについては、悪意のないのからあるのまで色々あったんですよ、噂が」
「やっぱり、彼女が芸能人だからですか?」
「ええ……、うちの高校はごく普通の進学校で、芸能人なんてミミちゃんだけだったものですから、色々な意味で全校の注目の的でしたからね、あのコ」
「憧れからシットまでってわけですね? よくわかりますよ、そーゆーの……」
うちの大学だってそうなんだ、多少は大人になっているはずの大学生だって、しかも今はもう「普通の大学生」になったミミちゃんに対してさえそうなんだから、高校生じゃあ無理もない話だ。 僕だってちょっと前までは高校生だったから、身にしみてよくわかるんだ。
「ミミちゃん、何でそんな高校選んだんです?
堀腰学園とか何とか、芸能人専門の学校だってあったでしょーに」
「そこがあのコらしいところなんですよ。
あのコの家はうちの高校の学区内なものですから、普通だったら、当然、うちの高校に来るはずなんです」
「なるほど、フツーのコが行く、フツーの学校で、フツーの高校生活がしたかったんですね。
わかるような気がしますよ」
「でも今から考えると、やっぱり無理だったんですねえ。
いくらあのコがそのつもりでも、まわりがそうは見てくれませんものね」
「すいません、どうも……」
「あら、荻須さん達は別ですわよ、よくわかってくれてますものね」
「それが……、伴ちゃんはともかく、僕はまだ自信ないんですよね、正直言って。
ミミちゃんのことが本当に理解できてるのか、変な目で見てないのかって……」
これは本当に今の僕の偽らざる気持ちだったんだけど、ありがたいことに、雪子さんはそんな僕に理解のこもった暖かい微笑みを送ってくれた。
「大丈夫ですよ、あたしにはよくわかりますから。
あのコがあんなふうに素直に自分を出しているのを見るのは、本当に久しぶりなんですよ」
「だといーんですが……」
「失恋した直後なんて、無理に明るく振る舞っているのがよくわかって、痛々しいぐらいだったんですよ。
『これからは人間を相手にしないで、学問に生きるのよ』なんて、冗談めかして言ったりして……」
ミミちゃんがそんな殊勝なセリフを言っている場面を想像して、僕は思わずクスリと笑いをもらしてしまった。 もちろんそれは今の明るく茶目っぽいミミちゃんで想像したからこそであって、実際には──そんな表情のミミちゃんはどうしても想像できないけど──もっと暗く沈んだミミちゃんの口から出たんだろう。
「それで、それまでのことを全部捨てて、新しく生まれ変わるつもりで、芸能界も辞め、なるべく普通の人が行かない大学を選んだらしいんです」
「それで、わざわざ変人揃いの理学部に……」
「あら、ごめんなさい、あたし、そんなつもりじゃ……」
「いーんですよ。
理学部って、変人っぽくて、人間嫌いな人が行くとこってイメージありますからねー。
なるほど、それで彼女、芸能人だった頃の話をできるだけ避けてるんですね」
「ええ、本当に親しい人の前以外では、絶対にその話はしませんでしたね。
でも大学に行って、荻須さん達を始め色々な人と出会ったおかげで、ようやく人間不信から立ち直ることができたみたいで、近頃はそれほどでもないようですけどね」
「ミミちゃんがそーだったなんて、今の話を聞いてもまだ信じられませんよ、僕には」
「それに、あたし、あやまらなきゃいけないんですけど、ミミちゃんの話を聞いているうちに、あたしも誤解してたことがわかってきたんです」
「と、言いますと……?」
「理学部に入る人なんて、科学を研究する人なんて、理知的で何事にも無感動な、冷たい人間だろうって思っていたんですよ、実は」
「……そー思ってる人、けっこう多いんですよね」
「それがミミちゃんの話を聞いているうちに、そーじゃないんだ、反対に子供っぽくて、何にでもすぐ感動してしまう人が多いんだなってわかったんです。
そして荻須さんと四条さんを見て、ああ、なるほどなあって実感したんですよ」
「ありがとーございます、理学部を代表してお礼を言わせてもらいますよ」
僕は照れ隠しに冗談めかしながらも、本心から彼女に向かって頭を下げた。 みんな誤解していて、この事をわかってくれる人ってのは案外少ないんだ、本当に。
「自然を相手にする科学者はですね、特にそーなんですよ。
僕等も先生からよく言われるんですけどね、オバケ見て、怖いって思わないような人は、科学者にはなれないって」
「……?」
今までこの話を聞かされた人と同じく、雪子さんもどうもよくわからないって顔つきだ。
「ちょっと考えると、反対みたいな気がするでしょ?
でもね、子供のように怖いって思う心から、好奇心や想像力がわいてきて、それが科学を発展させてきたんですよ、ほんとーは」
「……そう言われれば、そうかもしれないって気がしますわね」
「そーなんですよ。
何にでも感動して、何にでも興味を持つような、そんな子供心をなくしちゃーいかんのです!」
実はこの言葉は、いつも人に言いながら、同時に、自分自身に向かって言い聞かせている言葉でもあるんだ。 伴ちゃんのように根っから純真な人間と違って、僕のように世俗的なところのある人間は、いつも自分の心を励ましていないと、ついつい惰性に流されてしまうもんなんだ。
「荻須さん達を知った後ですから、あたしにもわかるような気がします」
「そー言えば、僕も、持田さんとミミちゃんにあやまらにゃならんことがあるんですよ」
「あたしと、ミミちゃんに……?」
「ええ、伴ちゃんのことなんですけどね。
僕、今まで、伴ちゃんのことをわかってくれるような女の子なんて、いて欲しいけど、ほとんどゼツボーじゃないかなって思ってたんですよ、ほんと言うと」
雪子さんは僕の言葉をどう受け取ったのか、あっけにとられたような顔をしてから、急にクスクスと笑い出してしまった。
「まあ、荻須さんったら……。女にだって人を見る目ぐらいありますよ」
「い、いえ、あの、そーゆー意味じなくて、何てったらいーか、その……」
「いいえ、そういう意味でしたわよ、今の言葉は」
雪子さんの優しくたしなめるような言葉に、僕は返事に窮してしまった。 そんな僕を彼女は優しく眺めながら、
「そりゃあ確かに、外見だけで人を判断するような女が多いのは、あたしも認めます。 でも、ミミちゃん、昔から芸能界に出入りしていて、色々な人を見てきてますから、あれでもけっこう人を見る目があるんですよ」
それから少し改まった口調になって、
「だからあたしも荻須さんを心から信頼してますし、こんな迷惑なことを頼んでしまう気にもなったんです」
と、笑い顔のまま僕の目をまっすぐ見つめた。 その瞳は、僕が思わずドギマギして目を伏せてしまったほど真面目な色に澄んでいた。
「め、迷惑だなんて、とんでもない! 喜んでやってますよ、僕は!」
これはお世辞でも負け惜しみでもなく、本当の気持ちだった。 雪子さんのような素敵な人と、たとえお芝居でも恋人同士になれるなんて、男として悪い気がするはずはないし、こんな貴重な体験は、残念ながら今後二度と再びあるとは限らない──はっきり言って、ほとんど望み薄な──出来事だろう。
「それに、まだなんとゆーか半信半疑なんですけど、ミミちゃんにそれほど信頼されたとゆーのも、ものすごく嬉しい気がしますよ」
顔が赤くなっているのが自分でも感じられたけど、誠意には誠意をもって返さなくてはと、僕は何とか雪子さんの目を見返すよう努力した。
「ほんとゆーと、ミミちゃんが僕等に相談を持ちかけた理由がさっぱりわからなかったんですよね、最初は」
「荻須さん達にしてみたら、そうかもしれませんね。
でもあのコ、前々から荻須さん達ともっと親しくなりたいと思っていたのに、なかなかきっかけがなかったみたいなんです。
そこへ、あたしが今度のことを相談したものですから、ちょうど良いきっかけができたってわけなんですよ」
「なるほど……、そうとわかったら、期待に応えるためにも、この役は何としても成功させないといかんですね!」
僕と雪子さんはニッコリと顔を見合せ、どちらともなく、無邪気にはしゃいでいるミミちゃん達を眺めた。
後から考えると、この時の雪子さんの微笑みの裏には、ミミちゃんに関してもうひとつの秘密が隠されていたんだけど、能天気な僕は、この時はまだそのことにほとんど気付いていなかったんだ。