
 3へ
3へ
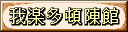
 webmaster@snap-tck.com
Copyleft (C) 2000 SNAP(Sugimoto Norio Art Production)
webmaster@snap-tck.com
Copyleft (C) 2000 SNAP(Sugimoto Norio Art Production)
昼食の時と同じく、夕食の場所もホールだった。 外は激しい雨が降り続いていて、ほの暗い中に、別荘から漏れ出る光に照らされた雨足だけが、レースのカーテンのようにキラキラと輝いている。 そんなちょっと寂しげな景色とは対照的に、ホールの中には別世界のように華やいだ雰囲気が満ちあふれていた。
昼間は気づかなかったけど、ホールの天井に豪華なシャンデリアがぶら下がっていて、それがこうこうと燈されているし、どこからともなく心地良い音楽が柔らかく流れて来るし、その場にいる人達も、これが昼と同じ人達かと目を疑うばかりに着飾っていて、あたりの空気をいやがうえにも華やかなものにしているんだ。 夢見心地というのはこういうのを言うんだろう、まるで自分がシンデレラ物語の登場人物にでもなったような気がして、足が地に着かないことはなはだしい。
派手に着飾った人々の間に入っても、キュートなミミちゃんと清楚な雪子さんは一際光輝く存在で、特にミミちゃんはじみなドレスにもかかわらずまばゆい燐光を放っていて、ホタルのように周囲から浮かび上って見えるのはさすがだった。 これがスターと呼ばれるような人が持つ特質なのだろうか、伴ちゃんが「見てるだけで、嬉しい気持ちにさせる」と言ったものを、ミミちゃんは確かに持っている。 僕は、いけない、いけないと思いながらも、チラチラとミミちゃんに目が行ってしまうのをどうすることもできないでいた。 この夢のような雰囲気の中で見る光輝く彼女は、僕にとって、やっぱり憧れの美少女スター「操ちゃん」になってしまうんだ。
やがて、恐怖のフルコースが始まった。 僕は隣の雪子さんを見ながら、フォークとナイフを武器にして、目の前に出されるモノ──内容はもちろんのこと、どこまでが食べられて、どこからが食べられないかという区別すらつかなかったんだ──に雄々しく戦いを挑み、華々しい惨敗を喫してしまった。 何しろ雪子さんの真似ばかりしていたもんだから、料理を味わうどころか、出されたものを全部食べることさえできなかったんだ。 と言うのも、雪子さんは女らしく少食で、給仕をしている女中さんもよく心得ているらしく、彼女には少ししか料理を盛り付けないもんだから、彼女のペースに合わせて食べている僕は、半分ほど食べたところで、もう次の料理に代わってしまう状態だったんだ。
料理が残された皿をさげながら、女中さんが「男のくせに何て少食なんでしょう」という目で僕を見ているのを感じて、コックさんに申し訳ないと思うと同時に、食べる事と寝る事だけが愉しみで、目の前に出された料理は絶対残さないことが自慢だった大食らいの僕にとって、それは無念極まりないことでもあった。
僕以上に食べる事が無上の愉しみである伴ちゃんは、ただひたすら目の前の料理を食べつくすことだけに没頭していた。 フォークとナイフを不器用に握って、危なっかしい手つきで必死に料理と格闘しながら、ひたむきに食事に取り組んでいる彼の姿は、滑稽を通り越して何かしら崇高なものさえ感じさせた。 隣の席のミミちゃんが、ヒナを世話する母鳥のように何くれとなく面倒を見てやっているし、彼女は雪子さんのように少食じゃないから──はっきり言って、僕や伴ちゃんといい勝負の大食らいなんだよ、実際──伴ちゃんは充分料理を平らげることができたようで、実にうらやましい限りだった。
僕と伴ちゃんの不慣れな様子を見て、正氏やその妹の裕美さんなんかは、小声でクスクスと笑ったり、わざと話しかけてきたりするんだ。 僕は料理と格闘することに必死で、かろうじてうわの空の返事をし、とても気のきいた話をするどころじゃなかったし、真正直な伴ちゃんは話しかけられるたびに食事する手を止めてしまい、例によって、早口で吃りながらも一生懸命真剣に返事をしようとしていた。 こんなからかいに対して、ミミちゃんと雪子さんは冗談で応酬し、うまく話の腰を折ったり、まぜっ返したりして僕等を援護してくれた。
不慣れな場所と不慣れな服、不慣れな食器と不慣れな食事、不慣れな人達と不慣れな会話──全く、こんなことが2、3日続けば確実にげっそりと痩せて、まさに「食べながら痩せるダイエット法」になるだろう。
食事が終わる頃、東京から耕平氏が戻って来て、みんなに挨拶をすると、女中さんに軽い食事を書斎に運ぶように言いつけ、そそくさとホールから出て行った。 社長ともなれば、椅子にふんぞり返ってむやみやたらに威張っていればいいのだろうと思っていたのに、どうしてどうして社長稼業もあまり楽ではないようだ。
食事が済むとテーブルがホールの隅に片付けられ、その場に流れていた柔らかい音楽が軽快なものに変るとともにボリュームも大きくなり、いよいよダンスパーティーなるものが始まってしまった。 ダンスのダの字も知らない僕は、ホールの隅っこに行って小さくなっていたい衝動にかられたけど、それでは役目が果たせないと思い、オズオズと雪子さんに尋ねてみた。
「あのー、やっぱり踊らなゃいかんと思うんだけど、踊り方知らないもんで……」
「大丈夫、大丈夫。
みんなの真似して、何となく体を動かしていればいいのよ」
彼女は元気づけるような笑顔を向けると、僕の腕を取って「さ、踊りましょう」と言う。 どうも、よく人真似ばかりしなきゃならない日だ。 これも我が身の無知を呪うべきか、それとも場違いなところに来てしまった無謀さを反省すべきなのか。
僕が躊躇していると、隣にいたミミちゃんが、
「踊ろ、伴ちゃん!」
と言うが早いか、返事も聞かず、戸惑う伴ちゃんを引きずって大胆にもホールの真中に出て行ってしまった。 そこで、仕方なく僕も雪子さんに引かれてすぐ後からついて行った。 他の人達も適当に相手を選んで踊りだしている。
僕は見よう見まねで、踊りらしきものをやりだした。 でも雪子さんのほっそりした手と柔らかい体に触れ、髪からなのだろうか、それとも体からなのだろうか、とにかくどこからともなく立ち上ってくるほのかな甘い香りに鼻をくすぐられ、どうしようもなく逆上してしまって、気がつくと、もう一曲目を終えてホールの隅で汗を拭っていた。 雪子さんが気をきかせて冷たいおしぼりを渡してくれたので、それで汗を拭き、ようやく少し冷静になって自分を取り戻すことができたんだ。
そこへ、伴ちゃんを引っぱってミミちゃんがやってきた。
「友規君、お楽しみのとこ悪いんだけど、伴ちゃんが、今度は雪ちゃんの相手したいんだって」
「へー、もうミミちゃんには飽きちゃったのかい?」
「そーなのよ。
もっときれいなコのほーがいーんだってェ。
ゼータク言ってんのよォ、伴ちゃんったら」
「そ、そんなこと言ってないよ、僕。
ミ、ミミちゃんが、今度は持田さんの相手しなさいって、そう言うもんだから……」
純情な伴ちゃん、上気した顔をさらに赤くして懸命に弁明している。
「あたしで良かったら、喜んでお相手するわよ、伴ちゃん」
と雪子さんはドギマギしている伴ちゃんの手を優しく取って、ミミちゃんに意味ありげな視線を送った。
「じゃ、伴ちゃん借りるわね。チーク踊っても、焼きもち焼かないでよ」
「まあ、雪ちゃんなら許すけど、他の人に貸したりしちゃだめよ、貴重品なんだから」
雪子さんと伴ちゃんがホールの中央に出て踊りだしたので、僕とミミちゃんもすぐ後からついて行って踊りだした。 今度は二度目だし、相手がミミちゃんだったので、最初ほど逆上はしなかったけど、彼女が気のおけない友達として信用し切った様子で体を寄せて来たりするもんだから、理性を失わないように必死の努力が必要だった。
「あのねえ、ミミちゃん……」
「何?」
「僕ねえ、一度、ミミちゃんに、あやまらにゃいかんと思ってたんだけど……」
「何を?」
ミミちゃんは茶目っぽい笑顔を僕に向けたが、僕がわりと真剣な顔をしてたせいだろう、笑顔の中にふと怪訝そうな表情が浮かんだ。
「実はねえ、今まで、ミミちゃんのこと、誤解してたもんでね」
「誤解……?」
「あ、いや、別に、誤解って言っても、悪い意味じゃないよ。
なんてーのか、もっと違う世界の人だと思ってたんだよ、ミミちゃんて」
ようやくミミちゃんの目に理解の色が表れて、それと一緒に心なしか寂しげな表情となった。
「あ、ゴメン。今はそんなふうに思ってないよ、もちろん」
「よくわかってるつもりよ、あたし」
「もちろん誤解してたのは最初の頃だけで、今回のことで色々と話せるようになってからは、ほんとのミミちゃんのことが、少しはわかるよーになったつもりだよ」
「いいのよ、誤解されるの慣れちゃってるから……」
と言ったミミちゃんの顔に、一瞬だけど暗い影がよぎったような気がした。 昼に海岸で雪子さんから聞いた人間不信のことが、彼女の脳裏をかすめたのかもしれない。
「ま、一種の後遺症みたいなもんね、ゲーノージン時代の」
「ゴメンね。
せっかくフツーの大学生になったってのに、みんなで『操ちゃん、操ちゃん』なんて大騒ぎしちゃって……」
「友規君のせーじゃないってば。よーするに、マスコミが悪いのよね」
「マスコミに踊らされる、僕等も悪いんだ」
「仕方ないわよ、それは。
でも、今の大学に入って幸運だったと思ってるのよ、あたし」
「幸運?」
「そう、ほんと運が良かったと思うわ。
友規君みたいに根っからのお人好しや、マスコミにも世間の噂にも踊らされない伴ちゃんみたいな奇特な人と、こうして友達になれたんだもん」
言葉は冗談めかしながらも、ミミちゃんの目は笑っておらず、真剣な色に澄んでいた。
「芸能界にいた時ね、ほんとの自分とは違う清純可憐な『南井操』を演じることに、ちょっぴり疲れちゃったことがあったのよね。 学校ではいっつもほんとの自分を出してたつもりで、友達なんかもちゃんとわかってくれてると思ってたのに、ある時ね……」
ミミちゃんはいつもの彼女らしくない静かな口調で、ポツリポツリと話を続けた。
「この人なら信頼できる、ほんとのあたしをわかってくれると思ってた人が、あたしの言葉よりも、根も葉もない変な噂の方を信じちゃって、大喧嘩しちゃったのよねー」
僕は黙ってミミちゃんの話を聞いていた。 雪子さんが言っていたミミちゃんの高校時代の失恋の話らしいので、どう返事をしたら良いのかわからなかったんだ。
「しかもその変な噂を流したのが、どーも、あたしが友達だと思って信頼してたコだったみたいで、それを知った時、すっごくショックだったのよね。 それで人が信用できなくなっちゃって、芸能界にも嫌気がさしちゃって、とうとう辞めちゃったのよねー」
目を伏せて、独り言のようにポツリポツリ話すミミちゃんの姿がいつになく頼りなげで可憐なので、彼女を抱きしめないでいるには、ものすごくつらい努力をしなければならなかった。 そんな気持ちをごまかすために、僕は強いて笑顔を作り、わざと冗談めかして言った。
「そーかぁ、なるほど、それが僕等操ちゃんファンをびっくりさせた、『謎の引退』の真相なんだねぇー」
僕の冗談めかした言葉を励ましと受け取ったのか、ミミちゃんは顔を上げると弱々しい微笑みを浮かべた。
「うん、週刊誌なんかに色々書かれてたみたいだけど、これがほんとにほんとの『知られざる南井操引退の真相』ってやつよ。
子供だったのよねー、あたしって。
今考えると、ほんとバッカみたい……」
「そ、そんなことないよ!」
思わず、ミミちゃんを抱いている手に力が入った。 彼女はそれでも僕を信頼し切った様子でなすがままになっていたので、恥じ入って、前よりも一層体を離す結果となってしまった。
「そんな目に会えば、誰だってそーゆー仕事が嫌になって、少しは人間嫌いになると思うよ」
「ありがと。
でも今の大学に入って、信じらんないくらい純真で、あたしがゲーノージンだったなんてこと、まるっきし気にしてない人とか、めっちゃくちゃお人好しの人とか、とにかく色んな人を知って、何となくまた、人間っていいなって思えるよーになったのよね」
ミミちゃん、ようやく普段のお茶目な彼女に戻って、照れ隠しの笑みを浮かべながら、
「でも、根が純情可憐な乙女なもんで、そーゆー人達となかなかお近づきになれなくって、けっこー苦労したのよねー、これでも」
「へー、根が純情可憐な乙女が、自分から野郎二人におかしな相談持ちかけるかなぁー」
やっといつものミミちゃんらしくなったので、ホッとして僕も調子を合わせ、後は冗談の応酬になってしまった。
そうこうしているうちに二曲目が終わったので、僕等はホールの隅に戻った。 伴ちゃんと雪子さんはもうすでに戻っていた。 そこへ、例の正氏がニヤニヤしながらやって来た。 正先生、派手なタキシード姿で、頭のてっぺんから足の先まで一分の隙もなくめかしこんでいる。
「やあ、操ちゃん!
彼氏は少しおいといて、今度は僕のお相手をしていただけませんか?」
「ええ、あたしで良ければ。
……伴ちゃん、ちょっといいでしょ?」
ミミちゃんが愛想良くそう答えたので、僕は少々驚いてしまった。 でも彼女が、伴ちゃんの許可を得るふりをして、僕等の方に意味ありげなウインクを送ってくれたので、遅まきながら、これも「お見合い粉砕大作戦」の一環なんだと合点がいった。 つまり、お見合いを邪魔するためには、要はこの正氏と雪子さんを近づけなければいいんだから、僕が雪子さんの相手をしても、ミミちゃんが正氏の相手をしても同じことなんだ。
とは言うものの、ミミちゃんが正氏と踊るというのは──我ながら了見が狭いとは思うけど──何となく面白くない気がしないでもない。
「は? ぼ、僕!? 僕は、もちろんいいけど……」
伴ちゃん、相変わらずミミちゃんのボーイフレンド役だという自覚がまるっきりない。 ミミちゃんがなぜ自分にそんなことを尋ねるのか、ほとんど理解できていない様子だ。
「それはそれは……!」
あまりにもあっさりとミミちゃんの承諾が得られたので、正氏もちょっと拍子抜けしたようだったけど、すぐにニタニタと相好を崩して伴ちゃんに顔を向け、
「じゃあ四条君、操ちゃんをしばらく借りますよ」
伴ちゃんが曖昧にうなずくが早いか、正氏はミミちゃんを連れてホールの中央に行ってしまった。
そこへ今度は、何を思ったのか正氏の妹の裕美さんがやって来た。 彼女は濃い化粧をし、胸元の大きくはだけたドレスを着て、見るからに豪華な真珠のネッレスをしている。 顔は美人と言えるんだけど、ちょっとした身のこなしにも、男の目を計算し、男を挑発するようなところがあって、僕の最も苦手とするタイプの女性なんだ。 昼食の時の紹介では、雪子さんと同じく大学の二年生だってことだったけど、大学生どころか、バーかキャバレーで働いている女の人のように変に大人びたところがあって、とてもじゃないけど同じ年には見えやしない。
「今度は、あたしのお相手をしていただけないかしら、荻須さん」
「え? い、いえ、あの、別に……」
「あら、あたしじゃ、おイヤかしら?」
「い、いえ、そーゆーわけじゃないんですけど、つまり……」
「だったら、踊りません? 女に恥をかかせるもんじゃありませんわよ」
助けを求めて伴ちゃんと雪子さんを見ると、すでに二人は、ミミちゃん達の後を追いかけるようにホールの中央に向かっていた。 仕方なく、僕は裕美さんに連れられてホールの中央に出て行って踊り出した。
「荻須さん、どこまでいってるんですの、彼女と?」
いたずらっぽい笑みを浮かべながら、裕美さんが僕の顔を覗き込むようにしてそう尋ねた。
「え?
どこまでって、どーゆうことですか?」
「まあ、とぼけちゃってェ……。
ABCのどこまでかってことよ、もちろん」
「エッ!?
あ、あの、ABCって、その、例のことなんですか、やっぱり……?」
「当たり前でしょ。
まだセックスまではいってないって見たんだけどな、あたし」
いきなりズバリと突っこまれて、どう答えていいかわからず、オロオロとうろたえてしまった。 雪子さんとそんなことまで打ち合わせてあるわけないし、第一、そんなこと、僕等には思いもおよばないことだったんだ。
「彼女、まだ処女みたいだし……。
それに、あなた知ってるんでしょ?」
「何をですか?」
「これが彼女とうちの兄貴の、体のいいお見合いだってこと」
「お見合い……ですか?」
かろうじて返事はしたものの、あまりうまくない芝居だったようで、すぐさま裕美さんに見破られてしまった。
「ウソがへたねえ、あなたって。
お見合いの邪魔するためにここに来てるんでしょ、あなた」
「……!」
「あたし、別に彼女に悪い感情持ってるわけじゃないのよ。
けど、ひょっとして家族になるかもしれないんだから、やっぱり興味あるじゃない、彼女に」
「それは、そーでしょーね……」
「あなた、彼女に利用されてるだけなのよ、わからないの?」
「えっ!?
利用って……?」
「彼女、この話いやなもんだから、あなた利用してつぶそうとしてるのよ。
けど、あなたのことは何とも思ってやしないのよ」
「ど、どーしてわかるんですか、そんなこと……?」
「女はね、好きな男に抱かれてる時には、あんなふうに、変に身構えて、しゃちこばってるもんじゃないのよ」
裕美さんの鋭いカン──これがいわゆる「女のカン」ってやつなんだろう──にはびっくりしてしまったけど、さすがの彼女も、僕が全ての事情を知った上で、進んで雪子さんに協力していることには気づいてないらしい。
「うちの兄貴もまだまだ遊び足りないみたいで、あんまり乗り気じゃないのよね、ほんとは」
「ほんとですかァ!?」
「ほんとよ。
乗り気なのは親達だけ」
「そーですか、みんな、嫌がってるわけですか……」
裕美さんの言葉に、僕は思わず笑みをもらしてしまった。 その笑みを目にとめたのか、裕美さんがいたずらっぽい表情で、
「嫌がってはいるけど、まだわかんないわよォ。
兄貴、女に手が早い方だから、その気になっちゃうかもね。
彼女、けっこう美人だし」
「だめですよ、そんなの!
せっかく僕が、僕とゆーものがありながら」
「ウフフ、お人好しね、あなたって。
彼女、あなたのことなんて何とも思っちゃいないのよォ」
「雪ちゃんがどう思っていよーと、僕は彼女の役に立てればそれでいーんですよ、ほんとーに」
色恋感情抜きで異性のために何かをするなんてことは、裕美さんにはとても考えられないことなのかもしれない。 僕のことを片想いの哀れな三枚目と思ってしまったらしく、軽蔑したような視線を僕に注いでいたけど、僕はあえてその誤解を解こうとは思わなかった。 そう考えてもらってた方が、こっちには何かと好都合なんだ。