
 第4章へ
第4章へ
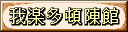
 webmaster@snap-tck.com
Copyleft (C) 2000 SNAP(Sugimoto Norio Art Production)
webmaster@snap-tck.com
Copyleft (C) 2000 SNAP(Sugimoto Norio Art Production)
中川さんが戻って来ると、僕等は人目を忍んで彼に会いに行った。 中川さんは展覧室の隣の管理室に寝泊りしていて、客の相手をしない時にはその部屋で休憩しているんだ。 休憩といっても、隣の部屋は耕平氏の書斎だし、絵の管理人も兼ねているわけだから、なかなか気の休まる時はないだろう。 サラリーマンは気楽な稼業だって聞いてたけど、なかなかどうして、けっこうつらい商売のようだ。
管理室はちょうど学校の宿直室のような感じで、部屋の東側の隅にベッドが置いてあり、北側の窓の下には事務机と腰掛けが、西側にはロッカーや事務用の本棚が整然と並んでいる。 部屋の中央には、一応、簡素ながら応接セットが置いてあって、暇をつぶすためだろうか、灰皿といっしょに将棋や雑誌がゴタゴタと置いてある。
中川さんは大喜びで僕等を迎えてくれ、僕の手を取って心のこもった握手をしてくれた。
「荻須君ですね! お礼を言う機会がなくて、どうもすいませんでした。
こんな迷惑な役目を頼んでしまって、ほんとに申しわけないと思ってますよ」
「いえいえ、いーんです。
僕の方こそ、何だか中川さんに悪くて……」
「何を言ってるんです、こっちから無理に頼んだことなんですから」
中川さんは、さっき絵の披露をしていた時とは違って快活そのものだった。 スポーツマンらしい日焼けした顔に絶えず笑みを浮かべ、生き生きとした表情をしている。 しっとりと落ち着いて、女らしく優しげな雪子さんと並べてみると、男らしく表情豊かな中川さんはなるほどピッタリお似合いの相手だ。
「それに、展示室では気を使ってもらってありがたかったですよ。 でも、気を使う必要なんてないですから、堂々と親密そうにして下さいよ」
僕のささやかなメッセージをちゃんと受け止めていてくれたんだ、この人は! この一言で、もう僕の気持ちをくどくどと説明する必要なんかないことがわかったけど、それでもやっぱり、一応はっきり口にしておこうと思った。
「どーもすいません。
あのう、こーゆー経験あんまりないもんで、どーゆーふうにしたらいいのか、よくわからんのですけど、なるべく、こう、ベタベタとはしないよーにしますから……」
「なーに言ってんのよ、ベタベタすんのが役目じゃない、友規君の」
ミミちゃんが、しょうがないわねえ、と言わんばかりの表情で口を出した。
「それに、彼氏公認で雪ちゃんみたいにきれいなコとベタベタできるなんて、そーめったにあるもんじゃないわよ、役得よォー」
「小山内さんの言うとおりですよ、荻須君。
どんどんベタベタしてもらって、構いませんから」
そう言うと、中川さんはいたずらっぽい視線を雪子さんにチラリと送り、
「もっとも、人によって好みってものがありますから、荻須君にしてみたら、役得か役損かはわかりませんけどね」
「まあ、失礼しちゃうわね、中川さんったら!」
雪子さんは憤慨したようにそう言ってから、今度は一転して甘えるような口調で僕に言った。
「役得ですよねェ、荻須さん?」
「はあ、そりゃまあ、いちおー、役得は役得ですけど……」
「いちおー、なんですの?」
「い、いえ、いちおーじゃなくて、もちろん、もちろんです!」
甘えるような口調は僕に対してではなく、当然、中川さんに対する罪のない当てつけだということぐらいわかってるけど、雪子さんのような美人にそんな口調を使われると、そういうことに慣れていない僕なんかは、オタオタとしてつい何でも言いなりになってしまう。
美人に弱いのは男という種族全体に共通する欠点で、例えばどんな重病人でも、美人の看護婦さんから、
「おかげんどォ? お元気そうねェ」
なんて、やたら甘い声で聞かれれば、つい、
「はい、もちろん元気です!」
なんて答えて、体操のひとつくらいやって見せるんじゃなかろうか。
「迷惑にならなければいいんですがね、荻須君の。
誰か、怒ってる人がいるんじゃないですか?」
「怒ってる人、と言いますと……?」
中川さんの言葉を理解できずに、ポカンとしていると、横からミミちゃんがからかうような口調で説明してくれた。
「ガールフレンドのことよ、中川さんが言ってるのは。
焼きもち焼かないかってこと」
「ガールフレンド!?
そんなもん、いるわけないよー。
いませんよ、残念ながら……」
「本当ですか?」
と、中川さんは信じられないという表情をしてくれた。 本当にそう思っているのか、それとも社交辞令なのかはわからなかったけど、まんざら悪い気がしないでもない。
「ほんともほんと、大真面目にほんとですよ。
だいたい、女の子なんてまわりにほとんどいないんですよね」
「荻須君、理学部でしたよね。
理学部なら、女の子も少しはいるでしょう?」
「いることはいますけどねえ。
なんてーのか、あんまり男とか女とかゆー意識ないんですよね、理学部のコは」
「ここにも理学部のコがいるんですけどね、友規君」
と言って、ミミちゃんが冗談半分に怒った顔を作って見せた。
「え? あ、ゴメン、変な意味じゃないんだよ、ほんと。
いやらしく女女してなくて、なんかこう、さっぱりしてて……」
「友規君、女心わかってないのね?
みんな、レッキとした女の子よ。
ただ女の部分を露骨に出して、男にコビ売るよーなまね、したくないだけなのよね」
「そーかもしれないね。
でも、とにかく僕はみんな気に入ってるよ。
やたら女っぽいのは苦手だよ、ほんと」
「雪ちゃん、女っぽいわよー。
友規君、そんなに嫌そーには見えないけどなー」
「持田さんは違うよ、女らしいのさ。
無理に女の部分を出さなくても、自然と中からにじみ出してくるんだよね。
そーゆーのはいーよ、別に」
「お世辞が上手ですね、荻須さんって」と雪子さんがニッコリと微笑み、「おだてられてるとわかっていても、つい嬉しくなっちゃいますよ」
「お世辞なんかじゃないですよ、ほんとーのことですよ!」
雪子さんの言葉に、僕は思わず真剣な声を出してしまった。
「荻須君はまだ知らないからね、本当の姿を。 今はネコかぶってますがね、これでけっこうおっちょこちょいで、ドジなんだから」
などと言いながら、中川さんの目は嬉しそうに雪子さんを見ている。
「まあ、ひどい!
ドジは秀昭さんの方でしょう?
あたしのこと、お手伝いさんと思ってたくせに」
「また、それを言う。
すみませんって、何度も謝ったじゃないかー……」
雪子さんは困ったような顔の中川さんを無視して、僕等にいたずらっぽい顔を向けた。
「中川さんったらね、あたしのこと、別荘で雇われているお手伝いさんだって思ってたんですよ、最初は」
「えーっ!
お手伝いさん……!?」
僕と伴ちゃんは思わず驚きの声をあげたけど、ミミちゃんはもう知ってる話なのか、クスクスと笑っているだけだった。
「ごめんなさいっ! すいませんーっ!」
と、中川さんが手を合わせて拝んでいるのに、雪子さんは相変らず無視したままだ。
「あたしがこの人と最初に会ったのは、この別荘なんですよね。
展示室の絵の整理で、父の会社から何人かの人が手伝いに来たことがあって、その時に初めて会ったんです」
「へぇー、それじゃあ、今みたいにやっぱり夏休みだったんですか?」
面白そうな話なので、僕は突っ込みを入れてみた。
「ええ。
暇だったので、あたしも絵の整理を手伝っていたんですけど、この人ったら、あたしのことをお手伝いさんと思い込んでいたんですよね」
「いやあ、彼女、あまりにも働き者でしたし、僕等に接する態度もすごく優しくて、何となく『社長令嬢』って感じじゃなかったんですよ」
中川さんはもう開き直った様子で、雪子さんの話にあいの手を入れた。 確かに雪子さんは僕が抱いている「社長令嬢」ってイメージと違って、上品でお嬢さんっぽくはあるけど、高慢なところもなければわがままなところもない。 何しろたいていの用事は自分でやるばかりか、暇があれば女中の白石さんの手伝いまでしてるようだ。 中川さんが雪子さんのことをお手伝いさんだと誤解してしまったのも、わからないでもない。
「それで、あたしもちょっぴり面白かったもんですから、この人に調子を合わせて、会社のこととか、父のこととか、色々話を聞いたんですよ」
「なるほど、なるほど」
「それで、絵の整理が終わった後、父があたしのことを会社の人達に正式に紹介してくれて、初めて娘だってわかったんですよね。
その時のこの人の顔ったら、ほんとなかったわ」
雪子さんは、その時のことを思い出したのか、クスクスと笑い出した。 その様子は、母親の静さんの少女のような笑い方にそっくりだ。 その笑顔につられて、中川さんに悪いと思いながらも、僕等も笑い出してしまった。 中川さんも苦笑いをしながら、しきりと頭をかいている。
「でも、その後で、秀昭さんとまた話をしてみると、言葉遣いは多少丁寧になったのに、話す内容は前とちっとも変わらないんですよね」
「前とちっとも変わらない、と言いますと……?」
「つまり、会社のことも父のことも、すごく真剣に厳しいことを言うんです。
一応、社長の娘相手なんですもの、社交辞令でもいいから、少しは誉めてくれてもよさそうなのに、秀昭さんったら厳しい言葉ばっかり」
雪子さんは、いつのまにか中川さんのことを名前で呼んでいる。 それが気を許してる時のいつもの呼び方なんだろう、すごく自然でいい感じだった。
「厳しい言葉ばかりじゃなかったさ、ちゃんと誉めるべき所は誉めたじゃないか。 自分でもはっきり言い過ぎかなと思ったけど、社長の娘とわかったとたんにコロッと態度を変えれるほど、僕は器用じゃないしね」
中川さん、もういいかげんに勘弁してくれって表情だ。 男らしい顔に少年のような困った表情が浮かんでいるのが、おかしな話なんだけど妙に可愛いらしかった。 彼は雪子さんから僕に視線を移すと、照れ隠しのように冗談っぽく言った。
「でも、おかげで、今だに彼女に頭が上らないんですよ。
何かというとこの話を持ち出されますし、何しろ社長の御令嬢様ですからねえ」
「ウソおっしゃい、御令嬢だなんて思ってもいないくせに……。
この人、あたしどころか、うちの父にだって平気でズバズバ文句言うんですよ」
「何も文句なんか言ってやしないさ。
ただ、いくら相手が上司でも、言うべきことはちゃんと言っておきたいだけで、無理に調子を合わせたり、何でも言いなりになったりはしたくないだけなのさ」
中川さんの口調には、相手にというよりも、むしろ自分自身にそう言いきかせているような調子があった。
「まあ、そこがいいとこなんですけどね、秀昭さんの」
「そこにまいっちゃったってわけよね、雪ちゃんは」
と、すかさずミミちゃんが雪子さんをからかう。 雪子さんは恥ずかしそうな顔で、ミミちゃんを冗談半分に睨んだけど、さりとてその言葉を否定しようとはしないんだ。
「要するに、世渡りがヘタなのさ。 サラリーマンとしてはあまり出世は望めないタイプだな、僕は」
今度は、中川さんの口調に少し自嘲ぎみな響きが感じられた。 僕にはまだよく理解できないけど、サラリーマンの世界には、いや大人の世界には色々とおかしなこと──と言っても、もちろん、僕等若者の目から見た時の話だけどね──が沢山あるんだろう。
この時、例によって今まで一言も口をきかずに、ポケーッとみんなの話を聞いていた伴ちゃんが、ボソッと言った。
「な、中川さんは、ど、どうして、こんな仕事してるんですか?」
「え? どうしてって聞かれても……。
ただ、会社がこの仕事をしろって言うのでしてるだけですよ。
なぜですか?」
「い、いえ、べ、別に、そう、たいしたことじゃないんですけど、ただ、何となく、こんな仕事、中川さんに、向いてないんじゃないかと思って……」
「やっぱり、そう見えますか?」
「あ、あの、へ、変な意味じゃなくて、もちろん、中川さんが一生懸命やってることは、よくわかるんですけど、ほんとは、もっと、こう、別の仕事をやりたいんじゃないかなって気がして……」
「ほう、別の仕事と言いますと、例えばどんなものです?」
中川さんは急に伴ちゃんに興味を持ったようで、伴ちゃんの顔を興味深げに眺めている。
「あ、あの、どうもすいません、こんなこと、言うつもりじゃなかったんですけど……」
「かまいませんよ。僕も興味ありますから、言って下さいよ」
「あたしもぜひ知りたいですよ、伴ちゃん」
雪子さんも興味を持ったのか、伴ちゃんの方に身を乗り出した。
「す、すいません、どうも……」
伴ちゃん、何気なく言った言葉が思わぬ反響を呼んだもんだから、ドギマギして盛んに頭をかいている。
「あ、あの、例えばですね、スポーツ選手のように、体を使う仕事とか、警察官のように、なんて言ったらいいか、こう、いつも力いっぱいやってる仕事の方が、向いてるんじゃないかと……」
「スポーツ選手か、警察官ですか……!」
中川さんは、びっくりしたような表情で伴ちゃんの顔をマジマジと見つめ、つぶやくように言った。 なるほど、スポーツマンタイプで正義感の強そうな彼は、秘書なんかよりもそっちの方がよっぽど似合っていそうだ。 雪子さんもミミちゃんも、納得した顔で何度もうなずいている。
「こりゃあ驚いたなあ、本当に……。
どうしてわかったんですか?
雪ちゃんにだって、まだ話したことないのに」
「あたしに……?
何、それ?」
と、雪子さんは解せない表情だ。
「実はね、僕は昔、スポーツ選手か警官になりたくてね。
憧れていたことがあったのさ」
「ヘえー、そんなことがあったの? すごいわねえ、図星じゃない」
「驚くだろ?
ねえ、どうしてわかったんです?
教えて下さいよ、四条君」
中川さんに問いつめられ、伴ちゃんはますますドギマギしながら、
「ど、どうしてって言われても、だ、だって、中川さん見てれば、誰だってそう思うんじゃないですか?」
「そんなことありませんよ、初めてですよ、こんなこと言われたのは」
「伴ちゃんにはね、不思議な超能力があるんですよ、中川さん」
と、ミミちゃんがまるで自分のことのように得意げな表情で説明を始めた。
「一目見ただけで、その人の本質みたいなもんを、ちゃんと見抜くことができちゃうんですから、ほんと」
「へえー、そりゃすごいなあ……」
「ほんとなんですよ、これ。
あたしの時だって、そーだったんですから」
「僕の時もそーだったね、確かに」
ウンウンとうなずきながら、僕もミミちゃんに同意した。 本当に、伴ちゃんにはそんな不思議な能力があるんだ。 そのくせおかしなことに、男女間の恋愛感情とかウソとか見栄とか建前とかいった、理屈に合わない複雑怪奇な人間の感情には、およそニブくて明き盲も同然なんだ。
「そ、そんなことないよ、いくらなんでも、一目見ただけでわかるわけないよ。 それに、少し話してれば、誰だってわかることだよ、そんなこと」
伴ちゃん、謙遜しているというよりは、こんなことがどうしてそう不思議なんだろうってな表情だ。 誰もが伴ちゃんのように純真な目で物事を見ているわけじゃないってことが、彼には理解できないんだ。
「へえー、不思議な人なんだね、四条君って……」
「あたしにもわかるような気がするわ、伴ちゃんに不思議な能力があるってこと」
雪子さんはもうすでに伴ちゃんのことを多少知っているので、中川さんほど驚いてはいないようだった。
「じゃあ、四条君、雪ちゃんはどうです? 彼女にピッタリの仕事は、何だと思いますか?」
中川さんの質問にみんなも興味を持ったようだ。 女らしく優しい雪子さんは、伴ちゃんの目にどう映っているんだろう?
「も、持田さんですか? そ、それは、当然……」
と言いかけて、急に伴ちゃんは不思議そうな顔で僕等を見回した。
「みんなも、ほんとは、わかってるんでしょ?
だって、誰だってわかるよ、そんなこと……」
「知らないわよ、ほんとに。
あたしだって、雪ちゃんとそんな話したことないのよ、今まで」
「あたしも、知らないんですよ、伴ちゃん。
あたしは、一体どんな仕事が向いているんです?」
ミミちゃんも雪子さんも、興味深そうに身を乗り出している。 もちろん尋ねた中川さんもそうだし、僕も興味しんしんといったところだ。 みんなが伴ちゃんの返事を待っていた。
「も、持田さんは、な、中川さんのお嫁さんですよ、もちろん」
いつものように伴ちゃんは真実味溢れる誠実そのものの態度で、冗談の色はこれっぽっちもない。
あっけにとられた僕等が大爆笑の渦に巻き込まれるまでには、ちょっとした間があった。 そのわずかな間に、またしても伴ちゃんがその不思議な能力を発揮したことを、伴ちゃんの言葉が本質的に真実に違いないことを、僕等の誰もが納得したのだった。