
 その10へ
その10へ
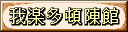
 webmaster@snap-tck.com
Copyleft (C) 2000 SNAP(Sugimoto Norio Art Production)
webmaster@snap-tck.com
Copyleft (C) 2000 SNAP(Sugimoto Norio Art Production)
人間が暦を用い始めたのは、農作業の目安とする必要があったためだと考えられています。 したがって日本の暦の起源も、農耕と同じように中国大陸や朝鮮半島から輸入されたものと思われます。 日本で最初に公式な暦が採用されたのは、飛鳥時代の西暦690年(持統天皇4年)とされています。 この時代の暦は1ヶ月は月の満ち欠けに基づき、1年は太陽の位置に基づいた「太陰太陽暦」でした。
1年を区分する指標となったのは、太陽が真南に位置した時にその高度が一番高い日、つまり二十四節気でいう「夏至」と、高度が一番低い日つまり「冬至」、さらにそのちょうど中間の日で、太陽が真東から昇り真西に沈む「春分」と「秋分」だと思われます。 これらは世界各地の古代文明に共通する区切りの日で、後に決められた二十四節気では、これらの日を「二分二至」と呼び、四季の中央の日としています。 そして、二分二至の中間の日から春夏秋冬の四季が始まるとして、立春・立夏・立秋・立冬の「四立(よんりつ)」が決められています。
農作業のサイクルから見ますと、冬至と春分の中間に位置する立春前後は農閑期にあたり、次のサイクルへの切り替わりの時期になります。 このため奈良時代あたりまでは、立春後の最初の満月の日を1年の始まりとし、収穫を神に感謝すると同時に、新しい年の豊作を祈願して色々な行事を行っていました。 これが正月の諸行事の起源と言われています。
その後、奈良時代の末期から平安時代にかけて唐の暦が取り入れられ、1年の始まりを立春前後の新月の日として、これを「元旦」と称するようになりました。 そしてそれまでの正月の行事を元旦に行うようにするとともに、唐の元旦の行事も取り入れて、現在のような伝統的な日本の正月の風習ができたと考えられています。 現在でも1月15日の古い正月のことを「小正月(または旧正月)」と呼び、古い正月行事を行う習慣が日本各地に残っています。 また南方系モンゴロイド民族の間では、現在でも立春後の最初の満月の日に、日本の正月とよく似た行事をする習慣があるということです。
江戸時代には日本はもちろん陰暦でしたが、長崎の出島にいた外国人は、現在と同じ太陽暦(グレゴリオ暦)を用いていましたから、陰暦の12月初旬にあたる太陽暦の正月に新年祝賀会を開いていました。 これを「オランダ正月」といい、日本人も何人か招かれていました。 このオランダ正月を見たり聞いたりした当時の江戸の蘭学者達は、それをまねて、太陽暦の元旦に新年祝賀会を開きました。 これを「蘭学者の新年宴会」といい、当時の日本では非常に先進的な行事でした。
このように、いかにも日本古来の風習と思われている正月の行事も、他の多くの日本文化と同じように、外国から輸入したものを、長い間かけて日本風にアレンジしたものなのです。
一般には、江戸時代に使われていた旧暦(宣明暦)は月の満ち欠けに合わせた太陰暦だと思われていますが、実際には1ヶ月を月齢(約29.5日周期)に合わせて29日または30日とし、1年を太陽の動き(約365日周期)に合わせた「太陰太陽暦」でした。 太陰太陽暦では何年か経つと季節と月がずれてしまうので、何年かに一度「うるう月」という月を入れて、季節と月のずれを調整します。 このため、うるう月がある年は同じ月が年に2回あることになります。
この暦では月の満ち欠けと日はぴったり合いますが、季節と月は年によって多少ずれるので農作業には不便です。 そこで1年を太陽の位置によって24等分し、「立春」から「大寒」まで24個の区切りをつけた、「二十四節気」という一種の太陽暦も併用して、農作業の目安としていました。 そして農閑期が正月になり、平均して立春前後に元旦がくるように、暦の基点を調整していたのです。
現在の新暦(グレゴリオ暦)は、キリスト教の祭りの都合で春分の日を3月21日にするように決められていますので、旧暦よりも1ヶ月ほど暦が進んでいます。 このため、旧暦から新暦に切り替わった1872年(明治5年)には1ヶ月ほどの期間がなくなってしまい、古来の季節感と暦とが1ヶ月ほどずれてしまいました。
例えば旧暦では、”新春”の元旦は立春前後であり、3月3日の”桃の節句”の頃には桃の花が咲き、5月頃には”五月雨(梅雨)”が降りました。 現在でも、年賀状に「迎春」と書く習慣が残っているのはこの名残です。 またお盆は元々旧暦の7月15日の行事でしたが、新暦となって本来の季節とずれが生じたので、”月遅れ”の8月15日に行うようになったのです。 色々なお祭りや神事も、季節感が重要なものは、新暦となってからは旧暦よりも約1ヶ月遅れの日付で行っているそうです。
| 1日 | ついたち・ひとひ |
|---|---|
| 2日 | ふつか |
| 3日 | みか |
| 4日 | よか |
| : | : |
| 10日 | とをか |
| 11日 | なかのついたち・とをかあまりひとひ |
| 15日 | もちのひ・なかのいつか・とをかあまりいつか |
| : | : |
| 21日 | とのついたち・はつかあまりひとひ |
| : | : |
| 30日 | みそか・つごもりのひ |
各月の日は上表のような名称でも呼ばれていました。 「ついたち」は「月立ち」に由来し、「晦日(つごもりのひ)」は、「月ごもり」つまり「月が消える」ということに由来し、「みそか」は「30日」に由来します。 さらに年の最後の日、つまり12月30日のことは「大晦日(おおつごもり)」と呼ばれ、その前日の12月29日は「小晦日(こつごもり)」と呼ばれていました。
現在では12月31日のことを「おおみそか」と呼んでいますが、この日は「おおつごもり」ではあっても「みそか」ではありませんから、本来は「おおみそか」と呼ぶのは間違いです。 強いて呼ぶとすれば、「おおみそかあまりひとひ」となるでしょうか。(^^;)
江戸時代に使われていた旧時刻制度は、季節によって時間の長さが変化する「不定時法」という非常に複雑なものでした。 まず真夜中と真昼の12時を「九ツ」とし、ほぼ2時間経つごとに「八ツ→七ツ→六ツ→五ツ→四ツ」と1ツずつ減っていき、四ツの次はまた九ツに戻ります。 そして太陽が地平線下約7度21分に位置する時の時刻、つまり日の出前約36分(後で述べる定時法の2.5刻)を「明け六ツ」、日没後約36分後を「暮れ六ツ」と称して、時刻の基準点としました。 このため1刻の長さは昼と夜で異なっているのが普通でしたし、季節によっても変化しました。 しかし毎日時刻を変えるのは面倒なので、二十四節気ごと(約15日ごと)に変える習慣でした。
| 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九ツ | 八ツ | 七ツ | 六ツ | 五ツ | 四ツ | ||||||
| 子 | →← | 丑 | →← | 寅 | →← | 卯 | →← | 辰 | →← | 巳 | →← |
| 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九ツ | 八ツ | 七ツ | 六ツ | 五ツ | 四ツ | ||||||
| 午 | →← | 未 | →← | 申 | →← | 酉 | →← | 戌 | →← | 亥 | →← |
ただし、これは幕府の天文方が定めた正式な時刻制度で、民間ではこの時刻よりも半刻(約1時間)ほど遅れた、九ツが午前1時頃に相当する時刻を用いていました。 まあ非常にのんびりとしてアバウトな時代でしたから、1時間ぐらいの誤差は何てことはなかったのでしょう。 ちなみに午後3時頃に食べる「おやつ」は、この民間の「八ツ」からきています。
また江戸時代の初期までは、「子の刻」から「亥の刻」までの十二支表示も用いられていました。 この表示法では、例えば「丑の刻」は、幕府時刻では午前2時を中心とした前後2時間、つまり午前1時から午前3時までのことです。 「草木も眠る丑三つ時」と言われる「丑三つ時」は、丑の刻を約30分ごとの4つに区分したうちの3番目の時刻で、民間時刻ではほぼ午前3時頃に相当します。 有名な「丑の刻参り」は、人に見られる危険性の最も少ないこの時間帯に行われたことに由来しています。
この旧時刻制度では、同じ時刻は季節にかかわらずいつも同じくらいの明るさであり、同じ時刻に仕事を始め同じ時刻に仕事を終わりますと、夏は長時間、冬は短時間の労働時間となります。 これは言わば「究極のサマータイム制」であり、照明設備の発達していない昔としては、ある意味で非常に合理的な時刻制度だと言えるでしょう。
また天文学者が天体観測などをする場合は、1日を100等分して100刻とした「定時法」を用いていました。 この場合の1刻は14分24秒に相当し、「一刻を争う」という言葉の「一刻」は、この1刻のことのようです。 つまり「一刻を争う」と言っても、せいぜい15分程度の時間感覚だったわけですから、当時は本当にのんびりと時間が流れていてうらやましい限りです。
日本人は昔から勤勉で働き者だったように思われていますが、日本人が時間に厳しい働き者になったのは、実は「欧米に追いつき追い越せ」をスローガンとして、富国強兵政策を行った明治時代になってからであり、時間に追いまくられるようになったのは、第二次世界大戦後の高度成長時代からのことです。 日本の長い歴史から見れば、これはごくごく最近のことであり、それまでの日本人はもっとのんびりとした時間感覚で生活していました。 時代を逆戻りさせることは不可能かもしれませんが、せめて心持ちだけでも、江戸時代のようにゆったりしたいものです。
算額とは、神社や仏閣に奉納した数学の絵馬のことです。 これは江戸時代中期の寛文年間の頃から始まった風習といわれ、現在、全国に約820面の算額が現存しているそうです。
江戸時代、日本全国で和算が流行し、和算の問題を出し合ってクイズのように楽しむ知的遊戯が流行しました。 そして難しい問題を作ったり、難しい問題を解いたりした人達が、それをみんなに見てもらうために算額を作って神社に奉納したのです。 当時、本職の和算家ならば和算の本を出版することができましたが、一般庶民ではそれは非常に難しいことです。 そこで算額を作って神社に奉納し、みんなに見てもらったわけです。
これはちょうどインターネットのウェブサイトやブログに、自分の趣味やアイデアを公開することと似ています。 つまり算額は、江戸時代における庶民の情報発信ツールだったわけです。 そして驚くべきことに算額に書かれた内容は数学的に高度なものが多く、中には西洋数学では100年以上経ってからようやく証明されたような、非常に難解な定理もあるそうです。
当時の和算と算額の流行は、関孝和という天才が出現したことが大きなきっかけです。 同じ頃、西洋ではニュートンやライプニッツといった天才が出現し、同じように数学を飛躍的に発展させました。 しかしその利用の仕方は、日本と西洋では大きく異なりました。
西洋では数学を主として科学技術と軍事に応用し、産業革命を経由して軍事大国になっていったのに対して、日本では主として科学と知的遊戯に応用し、知的大国・精神文化大国になっていったのです。 数学を知的遊戯に応用し、人生を豊かにするというのは、科学の究極の平和利用と言えるでしょう。 v(^_-)
算額は江戸などの都会に多いと考えがちですが、実際には東北地方などに多く残されています。 東北地方の農家では、農閑期の冬の間は大雪で娯楽が少なかったため、娯楽として和算が大流行したらしいのです。
江戸時代の東北地方の農家といえば、従来の教科書的には、江戸四大飢饉に代表されるように飢饉が多く、生きていくのに精一杯の惨めな貧しい生活というイメージがあると思います。 しかし意外なことに、江戸時代を通じて算額が最も多く奉納されたのは東北地方であり、その和算文化の担い手の多くは農民だったのです。
算額が沢山奉納されたということは、それを作った人が多かっただけでなく、その算額を見て内容を理解できる人が多かったということです。 何しろ内容を理解できる人が多くなければ、算額を奉納して自慢することなどできるはずがありません。 したがってこれまで抱いていたイメージとは違い、江戸時代の東北地方の農民は、貧しいながらも精神的に非常に豊かな生活を送っていたようです。
この東北地方の算額の存在を知り、今、お気に入りのイメージがあります。 それは江戸時代の冬の夜、雪深い東北地方の貧しい農家で、粗末な服を着たオジサンが、囲炉裏端で白湯をすすりながら、難しい和算の問題を楽しみながらじっくりと解いている、という情景です。
これと好対照な情景が、現代の冬の夜、郊外の建売住宅で、安物のガウンを着たオジサンが、ストーブにあたってビールを飲みながら、テレビのお笑い番組を見て能天気に笑っているという、数年前までの僕自身のイメージです。 σ(^^;)
そしてこれまで抱いていた”精神的に豊かな生活”というイメージは、都会のマンションの一室で、渋いながらも趣味の良い服を着たオジサンが、ワイン片手にバッハを聞きながら推理小説を読んでいる、という少々ステレオタイプな情景でした。
でも今の僕は、もし上記の3人のオジサンと知り合う機会があったとしたら、迷うことなく1人目の農家のオジサンと知り合いになりたいと思います。 その理由は、僕が数学関係の仕事をしているということだけでなく、1人目の農家のオジサンが一番興味深い話をしてくれそうだからです。
江戸時代は物資的には豊かではなかったものの、時間的余裕が豊富にあったため、物質文明ではなく精神文化を向上させ、世界に類を見ない精神文化大国になっていました。 しかもその精神文化は、人から与えられるものよりも自らが作り出すものが中心であり、人から与えられるものでも、茶道や華道や能のように、受け手が想像力を働かせて自ら参加して楽しむような文化が多かったのです。
2人目の建売住宅のオジサンはとりあえず無視するとして(^^;)、3人目の都会のオジサンが、既成の精神文化を享受するという受動的な楽しみ方をしているのに対して、1人目の農家のオジサンは、自ら精神文化に参加するという能動的でクリエイティブな楽しみ方をしています。 そんなオジサンなら、色々と興味深い話をしてくれると思うのです。 v(^_-)